内容説明
ケアが生まれる場では何が起こっているのか。社会の編成のあり方が変容し、家族と社会の境界が揺らぐなかで、さまざまなフィールドから民族誌的アプローチで迫る。
目次
ケアが生まれる場へ
第1部 福祉の試み、制度の隙間(高齢者ケアをめぐる共同性の再編―北部タイの郊外村の事例;最適化されたケア―フィンランドの社会サービス改革と「市民‐消費者」の浮上;家族と地域が重なり合う場―沖縄の離島における小規模多機能型居宅介護;福祉オリエンタリズムと人類学―ベトナムの村落における障害者ケアに見る「社会」の弱さ)
第2部 生の空間としての家族の境界面(ケアが動き出すとき―ラオス低地農村部の看取りの現場を事例に;死者への貢献の進め方―ガーナ南部における葬儀と集団の生成;津波のあとで、終わりの手前で―津波被災地域のケアと家)
第3部 異質な他者と出会う(宗教のケア・ネットワーク―占領下ドイツにおける避難民支援;街区のラーデン―1980年代ベルリンの再開発とケア;都市に生きる場所―タイにおける「寺住まい」の実践からみる社会再編;ケアの空間、かりそめの場所―東アフリカの難民キャンプにおける市場の形成)
第4部 隣り合う他者とのあいだで(乳のやりとり―下級武士の日記にみる江戸時代のいのち;あの虹の向こう―大阪市西成区の単身高齢者と世代・セクシャリティ・介護;マプーチェ医療とチリ人患者―サンティアゴの先住民医療の現場から;病気と付き合う―慢性病の食事療法をめぐる民族誌的試論)
著者等紹介
森明子[モリアキコ]
国立民族学博物館グローバル現象研究部教授。専門は文化人類学、ヨーロッパの民族誌研究。ウィーン大学経済史社会史研究所、ベルリン・フンボルト大学ヨーロッパ民族学研究所等にて客員教員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ゆう。
aof
-
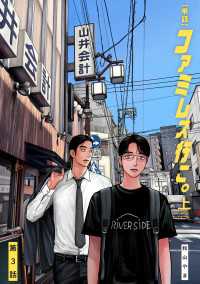
- 電子書籍
- 【単話】ファミレス行こ。 第3話 ビー…
-

- 電子書籍
- 【単話版】聖女、勇者パーティーから解雇…
-
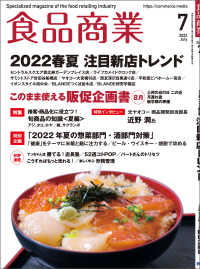
- 電子書籍
- 食品商業 2022年7月号 - 食品ス…
-
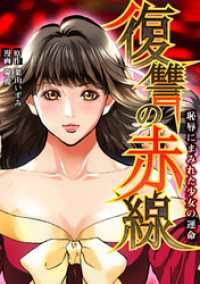
- 電子書籍
- 復讐の赤線~恥辱にまみれた少女の運命~…
-

- 電子書籍
- Cheese!【電子版特典付き】 20…




