出版社内容情報
19世紀から20世紀前半にかけてのドイツにおける軍事思想の発展については、主に政軍関係の転倒という観点から、その検証作業は多数なされてきた。第一次世界大戦における「総力戦」の出現によって、政治の手段としての戦争が自己目的化し、最終的には政治は戦争に奉仕すべきであると主張するルーデンドルフの独裁をまねくに至ったプロセスの分析に主眼を置いたものであった。しかし、プロイセン・ドイツの史的発展と不可分なドイツにおける軍事思想の発展は、モルトケによるドイツ統一戦争の勝利で頂点に達し、既にルーデンドルフの登場以前にシュリーフェンにおいて袋小路に陥り、様々な面で限界につきあたっていた。シュリーフェンの基本的コンセプトに従って行われた、第一次世界大戦の開戦劈頭におけるドイツ軍の西方攻勢が、ベルギーの中立侵犯によるイギリスの参戦とマルヌの戦いにおける敗北をまねいたことが、それを暗示している。モルトケ以降、なぜドイツ軍は最終的な軍事的勝利を手にすることができなくなったのか。またシュリーフェンは実際に勝利の栄冠を手に入れたわけではないにもかかわらず、その対仏作戦計画は天才的と称され、後世の軍人たちから高い評価を受けるようになったのは何故なのか。クラウゼヴィッツとルーデンドルフの間に位置するモルトケとシュリーフェンの軍事思想を比較検討することで、疑問に対する解答の一助を求めることにした。
内容説明
戦史や軍事史の叙述や解釈の前提となる軍事思想研究における本質的なアプローチとは何か?近現代ドイツの主要な戦略家や軍事史家の業績を通じて、戦争や戦場における経験を思想的に総括することの意義を考究し、実証史学では捉えきれない軍事的な真理の解明を図る論攷。
目次
第1部 モルトケとシュリーフェン(モルトケからシュリーフェンへ;モルトケとシュリーフェン;モルトケの遺産―ドイツ陸軍における作戦思想の変遷)
第2部 デルブリュックとその時代(ドイツ帝国海軍における運用思想の矛盾と対立;デルブリュックとドイツの世界政策;艦隊政策とデルブリュック)
第3部 第一次世界大戦とドイツ帝国(軍事思想から国防思想へ―総力戦のインパクト;総力戦とドイツ帝国―ミリタリズムに関する社会経済史的考察;軍事化の経済構造―体制類型としてのミリタリズムの成立に関する考察)
第4部 ドイツ軍事思想の諸相(クラウゼヴィッツの思想史的研究序説;戦略なき時代のクラウゼヴィッツ―戦間期のドイツを中心に;ドイツ空軍の成立)
著者等紹介
小堤盾[コズツミジュン]
1963年生まれ。早稲田大学大学院文学研究科博士課程満期退学。金沢工業大学国際問題研究所研究員等を経て、現在、軍事史研究家(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
-
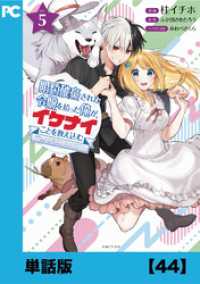
- 電子書籍
- 婚約破棄された令嬢を拾った俺が、イケナ…




