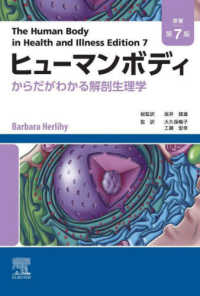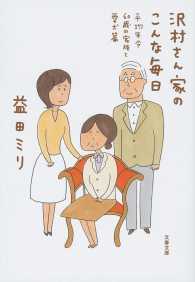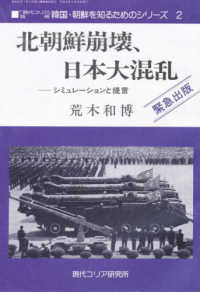出版社内容情報
なぜボストン美術館はアジア美術の宝庫なのか!
そのキーマン富田幸次郎の全貌!
富田幸次郎(1890~1976)は東洋美術コレクションで名高い、
米国ボストン美術館のアジア部長を戦前、戦中、戦後の32年間
(1931~1963)勤めた人物である。
「岡倉覚三(天心1863~1913)最後の弟子」と伝えられながらも、
日本では、その経歴や業績はあまり知られていない謎の人物でもある。
本書は、富田幸次郎の生い立ち、アメリカに渡った経緯、アメリカで
どんな人々に出会い、どのような活動をしたのかを探りながら人物像に迫り、
また、彼のアメリカにおける活動を解明することによって、20世紀前半の
日米間の緊張が高まるなかにあって、「ボストン日本古美術展覧会」という
一大イベントを成功させ、欧米人の日本文化への関心を多いに高めるとともに、
その後の日米文化交流の道を切り拓いた知らざる歩みを明らかにするものである。
目次内容
はじめに
第一部 ボストン美術館アジア部キュレーターへの道のり
第一章 父親、蒔絵師富田幸七──漆の近代を見つめて(1854~1910)
第二章 幸次郎の生い立ちと米国留学(1890~1907)
第三章 ボストン美術館──めぐり合う人々(1908~1915)
第四章 目覚め──美術史家として(1916~1930)
──アーサー・ウエーリと司馬江漢の落款をめぐる論争考
第二部 富田幸次郎の文化交流──日米戦争のはざまを米国で生きる
第五章 祖国に国賊と呼ばれて(1931~1935)
──『吉備大臣入唐絵詞』の購入
第六章 1936年「ボストン日本古美術展覧会」の試み(1936~1940)
──戦間期における日米文化交流の一事例として
終 章 太平洋戦争とその後(194 ~1976)
富田孝次郎年譜
内容説明
富田幸次郎(1890~1976)は東洋美術コレクションで名高いボストン美術館のアジア部長を戦前、戦中、戦後の32年間(1931~1963)勤めた人物。「岡倉覚三(天心1863~1913)最後の弟子」と伝えられながらも日本では、その経歴や業績はあまり知られていない謎の人でもある。
目次
第1部 ボストン美術館アジア部キュレーターへの道のり(父、蒔絵師富田幸七―漆の近代を見つめて(一八五四~一九一〇)
幸次郎の生い立ちと米国留学(1890~1907)
ボストン美術館―めぐり合う人々(1908~1915)
目覚め―美術史家として(一九一六~一九三〇) アーサー・ウエーリと司馬江漢の落款をめぐる論争考)
第2部 富田幸次郎の文化交流―日米戦争のはざまを米国で生きる(祖国に国賊と呼ばれて(一九三一~一九三五)―『吉備大臣入唐絵詞』の購入
一九三六年「ボストン日本古美術展覧会」の試み(一九三六~一九四〇)―戦間期における日米文化交流の一事例
太平洋戦争とその後(一九四一~一九七六))
著者等紹介
橘しづゑ[タチバナシズエ]
1954年、静岡県生まれ。長年、茶道と花道の研鑽を続ける。50歳を過ぎ、それらの学問的な裏付けの必要性を感じ、東京女子大学現代文化学部に編入し社会人学生となる。1990年代、夫(朝日新聞記者)の赴任に伴い家族で1年間ボストンに住み、豪華絢爛なボストン美術館の日本コレクションに驚いた経験をもつ。学部卒業論文ではボストン美術館アジア部長であった富田幸次郎をとりあげる。その富田が日本ではいまだ全く無名であることから、大学院時代には、二度の渡米調査を試みつつ独自に調査を重ね、博士論文「富田幸次郎研究―日米交流における役割」を執筆するに至る。東京女子大学大学院人間科学研究科修了。博士(人間文化学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Willie the Wildcat
志村真幸
こけこ
takao
-
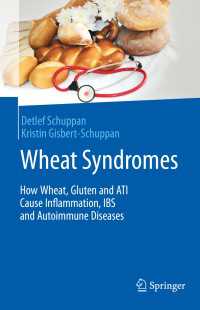
- 洋書電子書籍
- 小麦症候群:いかに小麦、グルテン、AT…
-

- 電子書籍
- サンデー毎日2016年7/17号