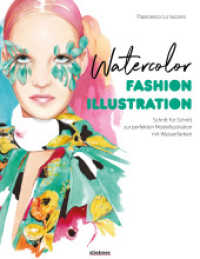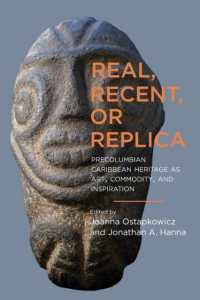- ホーム
- > 和書
- > 文芸
- > 海外文学
- > その他ヨーロッパ文学
出版社内容情報
人を喰うことは、常に神を喰うこと
私たちは神への深き愛ゆえに、神との融合を求めて聖餐を催し、その血肉に見立てたパンと葡萄酒を体内に取り込んで恍惚とする。だとすれば、兄弟たる人間へのフィリアゆえにその肉体を貪る行為も、貴き愛と呼べるだろう......
なぜ男は「美しいひと」を食べたのか。全篇にちりばめられた、古今東西の食人にまつわる膨大な逸話の引用から浮かび上がる、「真実の愛の行為」としての食人の姿とは。この、妖しい輝きを発する告白体の小説こそ、カニバリズム文学のイデアへの最接近を果たした奇書と呼んでも過言ではない。
内容説明
男は美しいひとを食べた―真実の愛ゆえに。全篇にちりばめられた、古今東西の食人にまつわる膨大な逸話。この、妖しい輝きを発する告白体の小説こそ、カニバリズム文学のイデアへの最接近を果たした奇書と呼んでも過言ではない。
著者等紹介
チェンティグローリア公爵[チェンティグローリアコウシャク] [Duca di Centigloria]
本名ヨハネス・クーデンホーフ=カレルギー(1893‐1965)。オーストリア=ハンガリー帝国公使であったハインリヒと青山光子の長男。ロンスペルクの領主であったが、二度の大戦で財産の大部分を失い、晩年はレーゲンスブルクで過ごす
大野露井[オオノロセイ]
1983年生れ。法政大学国際文化学部准教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- DVD
- パイレーツ・オブ・アイランド