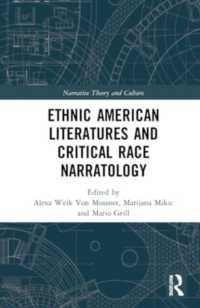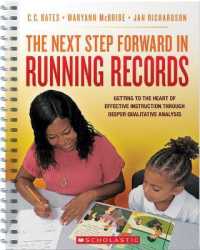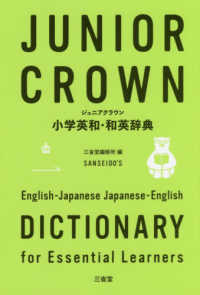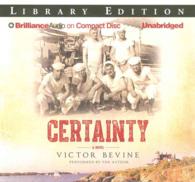出版社内容情報
【新版にあたって】
?「言語多様性」の語義および語用来歴についての
解説を2 ページほど増補!
?アラゴン語の言語法―言語法の国民党による改悪後、
国民党の州選挙敗北(2015)による再改正審議が
進んでいる点など、
2014 年7月の初版で好評を得、在庫もなくなりつつあり、
刻々と移りゆく言語多様性を改訂し、
新版として刊行致します。※ 細かな表現も刷新!
標準語一色、グローバル化のなかで英語一色に
塗りつぶされようとしている現在の言語社会にあって、
消えゆく言語を継承するために……。
イベリア半島の「弱小少数言語」ミランダ語、
王室のことばだったアラゴン語など欧州の少数言語、
そして、世界を席巻する新華僑のことば温州語や
加古川流域の「播磨ことば(播州弁)」などを
横断する知的冒険の旅。
衰亡に瀕する少数言語は、いかに保全され、
継承されるべきか、その可能性をさぐる!
寺尾 智史[テラオ サトシ]
てらお・さとし
1969 年、播州塩屋生まれ。加古川に育つ。
東京外国語大学卒業。
ポルトガル・スペインでの民間企業勤務ののち、
研究活動に入る。
神戸大学大学院総合人間科学研究科博士前期課程を経て、
京都大学大学院人間・環境学研究科
博士課程修了、博士(人間・環境学)。
神戸大学助教などを経て、
現在、宮崎大学教育文化学部准教授。
日本修士論文賞受賞(2007 年、三重大学出版会)。
著書に『多言語主義再考― 多言語状況の比較研究』
(共著、三元社、2012 年)など。
内容説明
「言語多様性」についてより深く考究した増補新版!
目次
第1章 ミランダ語―「むくつけき田舎なまり」から「ポルトガル唯一の少数言語」へ(イベリア半島における「弱小少数言語」の位相;むくつけき鄙の谷のファラ・チャラ ほか)
第2章 アラゴン語―王室のことばから谷底の俚言(パトワ)へ(アラゴン語か“アラゴン方言”か―外部からの再発見と同定;アラゴン語の東の果て―維持されるカタルーニャ語との接触 ほか)
第3章 少数言語保全と言語多様性保全との相克―アイデンティティ・ポリティクスの末路としての少数言語保全は言語多様性保全につながるか(少数言語保全と言語多様性保全―その関係性;ボリビアからの照応 ほか)
第4章 言語多様性は継承できるのか―東アジアからことばのグローバリズムを照らし返す(“上海語”のふしぎ―「言語内言語」再考;漢字という前近代的廃品は回収不可能か―「声と文字」再考からの取りかかり ほか)
第5章 液状化社会における言語多様性継承の可能性―その多層的舞台配置を母語環境から探る(播磨の奥(=加古川流域の中心)と近代「地方語詩」の黎明
播州ことばというスティグマ ほか)
著者等紹介
寺尾智史[テラオサトシ]
1969年、播州塩屋生まれ。加古川に育つ。東京外国語大学卒業。ポルトガル・スペインでの民間企業勤務ののち、研究活動に入る。神戸大学大学院総合人間科学研究科博士前期課程を経て、京都大学大学院人間・環境学研究科博士課程修了、博士(人間・環境学)。神戸大学助教および、東京外国語大学、神戸大学、京都大学、東京大学、立命館大学、京都精華大学、共立女子大学、放送大学非常勤講師を経て、宮崎大学語学教育センター、大学院教育学研究科准教授および中国浙江師範大学外国語学院客座教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。