内容説明
18歳でホントに「新しい」新作落語を志し、落語界の「新作確信犯」といわれる円丈による21世紀落語論。落語理論と現状分析、新作落語の作り方、そして落語の演じ方まで、円丈の落語理論のすべて。
目次
第1部 落語論(落語を考える)
第2部 落語台本論(円丈のギャグ進化論;落語はどうやって作るのか;発想による落語のストーリー構築法)
第3部 落語演技論(円丈の落語演技論)
円丈写真館
著者等紹介
三遊亭円丈[サンユウテイエンジョウ]
1944年名古屋市生まれ。明治大学文学部演劇学科中退。高校時代より落語家を目指し、6代目三遊亭円生に入門。「ぬう生」となる。13年の厳しくも苦しい修業を経て「円丈」で真打。新作落語で頭角を表し、ラジオ・テレビで活躍。新聞・雑誌のコラムも執筆。現在、落語協会監事(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
落語の愉しみ本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
いくっち@読書リハビリ中
7
誰も彼もが落語論を出版する。少々食傷気味だが、円丈師匠が書いたからこそ読めるというもの。「落語論」と「台本書き」と「演ずる」に分けたから「ろんだいえん」。そんなネーミングから師匠らしいや。面白いところもあるけれど、まとまりがないから読みにくいかな。文章の統一性が欲しかった。落語家の書き物にそんなことを求めちゃだめかしら。円生師匠に弟子入りした気持ちと理由がわかったからまあいいや。円丈自作落語事典は素晴らしいです。それにしても1800円とは結構お高い。2009/07/28
bluemint
6
落語を論じて、台本を書いて、人物を演ずる。軽く見られつつも新作落語に全精力を傾けて戦い抜いた三遊亭円丈の渾身の一作。本人は遺言と言っているが、本人が持っている落語についての想いをぶち撒けている。最近野球の大谷が同じようなことを言っていたが、師匠の芸に惚れたらもう一生その芸を超えられない。批判的に乗り越えていくからこそ落語が発展していくのだ。笑いは緊張と緩和、と言ったのは桂枝雀だと思っていたが、元はカントらしい。恐怖は緩和からの緊張。怪談は日常の中に突然出現する非日常。2023/08/25
kera1019
6
「新作がウケても、ウケない古典をみんな聴いている。」古典落語にシカトされ続けた円丈落語、どのお笑いジャンルでも自分でギャグを作ってる時代に「どうして古典に入門するの?意味がわからない」…古典をそのまま演ってたら落語の命脈は尽きる。大衆芸能には[今]が大切なのだ。新作なら誰にも負けないと大声で唾を飛ばし力いっぱいやるのが円丈師匠の魅力。若干、空回り気味なのも含め、負けず嫌いで自分が大好きな円丈師匠らしい一冊でした。2014/03/26
か〜ら
6
台本論、演技論何れにも、円丈師の徹底した研究分析の姿勢、落語に対する厳粛な向き合い方が伺える。然し第一部、落語論の熱気溢れる語りこそが一冊の要だろう。『御乱心』を彷彿とさせる強烈な筆致。これは苦い薬として提出された本だ。円丈写真館から円丈作品事典までが収った充実の一冊だが、誤字が多い。編集者しっかり仕事するべし。2009/06/07
君吉
5
その場で思いついたことを片っ端から書いてる感が全体的に漂ってて、誤字脱字も多くて編集も酷いし、しかもほとんどの項目の締めが己の自慢に結びついでいくのもなんか可愛らしいけど、単に苦笑して見過ごしてはいけない功績の数々はやはり圧倒的に偉大! 実践的な技術論や方法論も勉強になるけれど、とはいえなにより、やっぱり理論よりは思いっきり感覚でやっておられる方だということを読めば読むほど実感できたのが嬉しかった。2011/01/09
-

- 電子書籍
- 婚約破棄で幸せを諦めた私ですが、 女嫌…
-
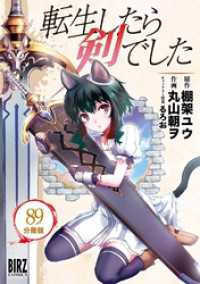
- 電子書籍
- 転生したら剣でした 【分冊版】 89 …
-

- 電子書籍
- 民謡の発見と〈ドイツ〉の変貌 - 十八…
-

- 電子書籍
- 劇場型社会の構造 「お祭り党」という視…





