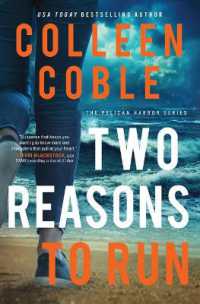内容説明
コミュニティデザインの第一人者がその源流を求めて、激動の19世紀イギリスを生き抜いた先人たちの思想をたどる。カラー図版多数収録。
目次
第1章 師匠ジョン・ラスキン
第2章 兄弟子ウィリアム・モリス
第3章 使徒アーノルド・トインビー
第4章 姉弟子オクタヴィア・ヒル
第5章 発明家エベネザー・ハワード
第6章 楽観主義者ロバート・オウエン
第7章 哲人トマス・カーライル
著者等紹介
山崎亮[ヤマザキリョウ]
1973年、愛知県生まれ。studio‐L代表、東北芸術工科大学教授(コミュニティデザイン学科長)。2005年、studio‐Lを設立。地域の課題を地域に住む人たちが解決するための「コミュニティデザイン」の先駆的実践者として、日本全国で住民参加型の総合計画づくり、建築やランドスケープのデザイン、市民参加型のパークマネジメントなどに取り組む(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
33
モリスは「人が労働から喜びを得ることが可能だということを指摘したのはラスキンが最初ではない。ロバート・オウエンは協同性と善意によって労働が辛いものじゃなくなる」と述べ、シャルル・フーリエは勤労意欲を高めることと合理的な配分が必要だとしている。どちらも労働を苦痛ではないものにしようと考えて。ラスキンは違う。仕事のなかに芸術的な喜びを見出すことの重要性を指摘、それを社会や政治のあり方にまで拡大して述べている(15-16頁)。ラスキンは、建築の装飾に三種の装飾。隷属的装飾。規範遵守的装飾。革命的装飾(18頁)。2018/09/24
福島雄一
3
コミュニティデザインを組み立てて継続していくためには コンテクストってやっぱり大事なんだなと 1年ほどイギリスに滞在していたことがありますが、コミュニティ文化が豊かで文化的な奥行きを感じつつ、 階級社会がかなり強固だからなのかな?と思うこともしばしばありました。 2017/01/03
Tenouji
3
手間を惜しまない仕事で経済的にバランスを取ることは難しいんだな。2016/07/31
nizimasu
3
著者の山崎さんは情熱大陸なんかにも出る有名人だけどその思想の根幹にラスキンやモリスが出てくることに驚いた。それはアーツ&クラフト運動が産業革命以降のイギリスで起きた労働の阻害の問題と日本の地域社会の振興との問題をシンクロさせているという点で山崎さんの原点ともいえる問題意識なのだろう。個人的にモリスはラファエル前派に繋がり自分のファンタジーなイメージの源泉にあるもの。イギリスの憧憬はさらにいえばロックを生んだ国でもある。モリスといい民藝といいどうも自分の琴線に触れるテーマで社会運動キライの自分の胸騒ぎに驚き2016/06/19
Shohei I
2
コミュニティデザイナーとして活躍する著者がその思想の元となったイギリスの先人たちの活動と思想をまとめた一冊。 産業革命期のイギリスという人としての生き方や働き方が大きく変わるタイミングで、コミュニティについて考えた人たちの行動は今の時代にも活かせることが多々ありました。 「私がこの世からいなくなったとき、友人たちが私のやり方を盲目的に踏襲しないことを願っています。状況が変われば、違った努力が必要になるはずです。永続させるべきなのは私たちの運動の精神であって、精神を失った形式ではありません」(本書より)2019/08/03