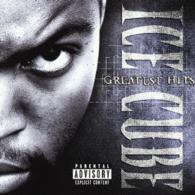内容説明
国家といかにつきあうか。主権、憲法、民主主義、新自由主義を歴史的な根源から問い直す、二一世紀の政治哲学!
目次
第1章 主権を超えていく統治―特定秘密保護法について(特定秘密保護法の成立;公開性の原則は本当に可能か? ほか)
第2章 「解釈改憲」から戦前ドイツへ(「解釈改憲」の意味;「集団的自衛権」の本質 ほか)
第3章 主権概念の起源とその問題(主権理論における行政の位置づけ;主権理論の完成者・ルソー ほか)
第4章 新自由主義の統治をめぐって(ナチスとオルド自由主義;フーコーのオルド自由主義評価 ほか)
第5章 立憲主義と民主主義再考(構成的権力;立憲主義と民主主義の不一致 ほか)
著者等紹介
大竹弘二[オオタケコウジ]
1974年生まれ。南山大学外国語学部准教授。専門は政治思想史
國分功一郎[コクブンコウイチロウ]
1974年生まれ。高崎経済大学経済学部准教授。専攻は哲学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
20
國分先生:TPPで日本市場はどうなるかわからない。日本郵政も米国資本に乗っ取られることも。NSCで自衛隊も米国に使われるかも(60頁)。由々しき事態。大竹先生:19C半ば、資本主義による貧困問題、社会問題が深刻化。 不平等をただす国家の役割が重視(124頁)。民主主義は集団的アイデンティティに立脚すると考える(251頁)。 個人の自由や権利に立脚すると考えないようだ。私は民主主義は集団と個人の相互作用ではないかと思うが。 2015/03/11
またの名
10
国家統治のあり方を巡りシュミットやベンヤミンが言及されつつ経営の父ドラッカーに還るべきではという結論に収束していく、十年後の視点からの答え合わせが楽しくも悲しい対談。「論理学的に言えば、改憲にはメタ/オブジェクトの区別に関わるややこしいロジカルタイピングの問題があるわけですね。学者のあいだで、96条の手続きによって96条を変えられるかどうかが一時期かなり熱心に議論されていたらしい。当時はこんな形而上学的な議論をしていて何の役に立つんだろうとも思われていたそうですが、実際に、改憲しにくいのであれば96条を…2024/04/16
かんがく
8
政治思想を専門とする2人による対談。主権と行政、立憲主義と民主主義など普段なんとなく使ってしまっている言葉について、シュミットやスピノザなど様々な思想家の言説を用いつつ丁寧に語られていくので、とても面白い。「はじめに」と「おわりに」で書かれているように、ラディカルに根っこから概念を検討することの有効性がよくわかった。2022/04/01
くり坊
6
今月の課題図書、予想外に時間がかかりました。政治の話が苦手分野なせいかな。対談なので、もっとサクッと読めるかと思っていたけど。//メモ: 「実際に法をつくり出すのは法解釈である」法の運用と改憲の問題 / ホッブズ「リヴァイアサン」、政治実用っぽい上手い邦訳書名がつけられていたら、日本人にも実際にもっと読まれて、私たちは主権についての理解を深めていたのであろうか。リヴァイアサンって文学チックなタイトルだな、と改めて感じいる。 / ダリデ「あらかじめ『これが正義である』と決めることはできない」非合法について2015/02/25
T F
4
立憲民主主義の土台を掘り崩したという点で、安倍政権は戦後最悪の政権の一つに入ると思う。ただ、国家に対する懐疑というのは世界的な潮流で、アメリカ大統領がトランプからバイデンに変わってもトランプ現象ともいえる流れが変わるとは思えない。グローバルで見れば国家は小さすぎるが、ローカルに見れば大きすぎる。グローバル時代にあった統治機構を生み出す必要があるだろうが、政治学の世界でそうした試みはあるのだろつか。公開性や民意を組み取る仕組みの複線化などはおろそかにできないとしても、もっと大きな転換が必要な時期かとも思う。2021/01/03
-

- 電子書籍
- 悪霊だけど死神に恋しました【タテヨミ】…
-

- 電子書籍
- ポケットビリヤード大全