内容説明
吉野ケ里遺跡や平塚川添遺跡を含む最新の情報・データ、あらゆる古文献・発掘資料などを数理文献学や内容分析学といった科学的な方法で分析整理し、天照大御神と卑弥呼の活躍する時代を特定。天照大御神は卑弥呼の神話化した姿だったことを明らかにする。
目次
プロローグ 「箸墓=卑弥呼の墓」年代捏造事件
第1章 卑弥呼の生きた時代―『魏志倭人伝』にみる古代日本
第2章 卑弥呼はだれか―三つの説を追う
第3章 「高天の原」はどこか―神話の舞台を科学する
第4章 邪馬台国への道―女王の都するところ
第5章 卑弥呼の死―古代の空に二度の皆既日食
第6章 大いなる発見 平塚川添遺跡の発掘―大環濠集落の出現
著者等紹介
安本美典[ヤスモトビテン]
1934年、中国東北(旧満州)生まれ。京都大学文学部卒業。文学博士。産業能率大学教授をへて、現在、古代史研究に専念。「季刊邪馬台国」(梓書院発行)編集責任者。「邪馬台国の会」を主宰。情報考古学会会員。専攻は日本古代史、言語学、数理文献学、心理学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
mazda
21
これまで古事記や日本書紀を読んでいて疑問に思っていたのが、古い時代の天皇の寿命の長さでした。これについては、当時の日本では今の1年を2年にカウントする暦を使っていたのかも知れない、ということから逆算すると、おおよそ平均的な寿命になるようです。これらを元に線を引くと、卑弥呼が活躍したとされる時代が天照大御神の時代と合うようです。また、邪馬台国が九州というのも支持されるようですし、総じてこの説で合っているのかな、と感じます。昔の人たちがどういった思いでこのような記録をつけたのか、ロマンがあります。2016/08/08
長島芳明
2
邪馬台国関連では、安本美典氏が一番説得力があると思う。記紀神話と魏志倭人伝の類似点や、発掘された一次史料の解説。そして統計学や地名学を引き合いに出して総合的に網羅している。彼の本をいくつか読んできたが、この本が一番な気がする。
俊介
0
いろいろな角度から分析を加えて、卑弥呼は天照大御神であり、邪馬台国は大和政権説を主張している。特に著者は「情報科学」による分析を重んじるのだが、言わば、状況証拠主義と言えるだろうか。対して考古学は物的証拠主義と言える。そしてその物的証拠主義の孕む危険性は、考古学が過去に捏造事件などを起こしたという事実によって確認される。本書の冒頭でもそういう問題が論じられている。もちろん物的証拠が全く無意味なんてことは主張しない。著者の説を裏付けるものとして、遺跡での発掘も取り上げられる。個人的には状況証拠主義が楽しい。2019/01/23
-

- 電子書籍
- 彼女のためにクズになった男 【分冊版】…
-
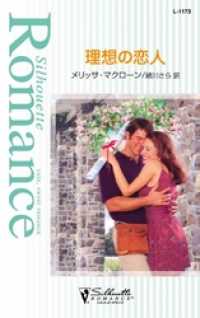
- 電子書籍
- 理想の恋人 ハーレクイン
-
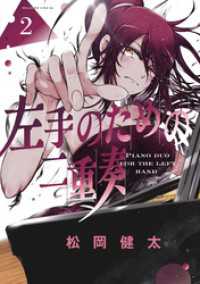
- 電子書籍
- 左手のための二重奏(2)
-
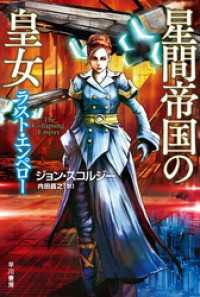
- 電子書籍
- 星間帝国の皇女-ラスト・エンペローー …
-
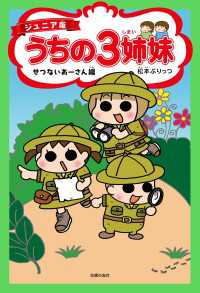
- 電子書籍
- ジュニア版 うちの3姉妹 せつないあー…




