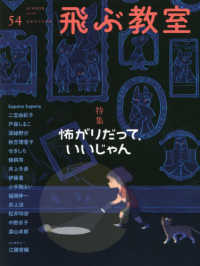出版社内容情報
内容説明
人新世というかつてない時代を生きるには、“文化人類学”という羅針盤が必要だ。ボルネオ島の狩猟採集民「プナン」と長年行動をともにしてきた人類学者による、“あたりまえ”を今一度考え直す文化人類学講座、開講!!
目次
第1章 文化人類学とは何か
第2章 性とは何か
第3章 経済と共同体
第4章 宗教とは何か
第5章 人新世と文化人類学
第6章 私と旅と文化人類学
著者等紹介
奥野克巳[オクノカツミ]
立教大学異文化コミュニケーション学部教授。1962年生まれ。82年メキシコ先住民の村に滞在、83年バングラデシュで上座部仏教僧、84年トルコを旅し、88~89年インドネシアを一年間放浪。94~95年ボルネオ島焼畑民カリス、06年以降同島狩猟民プナンのフィールドワーク(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
trazom
114
社会を形成する諸原理(家族、性、民主主義など)に揺らぎが生じつつある現代において、文化人類学という学問は大変重要だと思う。本書では、ボルネオ島での著者の研究を踏まえて、性/経済(贈与、交換)と共同体/宗教(儀礼、呪術)/自然(人間、文化と自然)の各テーマについて、文化人類学的な考察が紹介される。現地の人々の考えや行動を、フィールドワークという手法によって虚心坦懐に理解しようとする姿勢を通じて、西洋的な文明進化論、自文化中心主義、人間中心主義という現代のパラダイムに対する根本的な問いが生まれる気がする。2022/11/10
樋口佳之
58
プナンの人たちの神話が、「文化」から「自然」が生まれたと考えたように、多くの先住民社会では、しばしば人間以外の諸存在も、人間性を有していたと見ている…それは、複数種によってこの世界は作られ、営まれていることに、これまで人類学が出会ってきた先住民の人々は気づいていたということ…「存在論的転回」を経た人類学は、改めてそのことに立ち返ろうとしています。/とても視野の広い議論でかつ論旨明快。これから何を学ぼうかと選択に入っている世代にお勧めだし(または危険)、数十年前に読みたかったかも。/ご紹介に感謝でした。2022/09/21
to boy
23
文化人類学というとアマゾンなど未開の部族を調査して、こんな風習があるといった上から目線のものだと思っていたらとんでもない間違い。他の民族の中に入りその文化を学ぶことで自らの文化の意味を見直すきっかけになり、先進国とか未開という概念を無くし人類とは何者かを探るものだと分かった。さらに最近では人新世という概念から人類だけでなく他の動植物、自然を含めた大きな概念を想定しその中の一つである人類という考え方が出始めているとのこと。文化人類学の奥深さをちょっと覗いた気分でした。2023/12/28
ta_chanko
22
世界各地の狩猟採集民の生活を見ると、人間の多様性に驚かされる。自分たちの現代的?な生活が普通で先進的だと思ってしまいがちだが、長い人類史の中でみれば数多の文化の一つに過ぎない。近年、現代世界でもLGBTの権利が認められるようになってきたが、狩猟採集民の性の多様性は想像を超えていた。また近現代は「所有」という概念から資本主義経済を発展させてきたわけだが、「所有」しないことが名誉である社会も存在する。人間が自然を支配・利用するのではなく、文字通り自然と共生する生き方もある。視野狭窄に陥らないための名著。2022/09/06
テツ
19
あたりまえのことだけれど、文化が異なればベースとなる道徳観や価値観も大きく異なる。自分たちが慣れ親しんでいるそれらとは大きくズレたものをベースに生きている人々を目にしたときには優越感や蔑み、敵意すら抱きがちだけれど、これも当然のことながら「違う」というだけで、上下関係にはない。そうした差別意識がゼロになることなんてありえないのだけれど、世界を広く眺めることによって民族間だけではなく、個人間の「違い」にもおおらかになり、良い意味で「違い」を放ったまま共存できるメンタルを養える気がします。2023/03/08
-
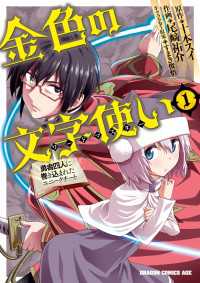
- 電子書籍
- 金色の文字使い1 ―勇者四人に巻き込ま…