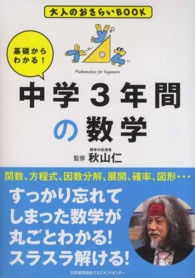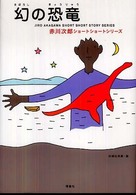目次
3 各鉄道・軌道使用例(続き)(河南鉄道→大阪鉄道;播州鉄道→播丹鉄道;篠山軽便鉄道;中国鉄道;小野田軽便鉄道;阿南鉄道;博多湾鉄道;小倉鉄道;筑前参宮鉄道;東肥鉄道―九州肥筑鉄道;九州電燈鉄道→東邦電力)
4 鉄道院→鉄道省→運輸省(ガンツ式;工藤式)
5 1940年以降の蒸気動車使用例(西武鉄道;名古屋鉄道;名古屋近辺軍需工場;博多湾鉄道汽船→西日本鉄道;鹿本鉄道;熊延鉄道;国東鉄道;口之津鉄道→島原鉄道)
6 機関・走行部のみ再生事例(三菱造船長崎造船所;台湾総督府納品機関部;大阪瓦斯京都工場5)
7 客車としての購入事例(天塩鉄道;常総鉄道→常総筑波鉄道;江若鉄道;芸備鉄道)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
rbyawa
0
d032、そもそも上巻を読む時点で蒸気動車ってのがどういうものなのかも理解してなかったんですが、客車と運転台が一体になってるもの、と考えていたら客車単体もあるじゃん! ただガソリンカーの代替として出てくること考えると走行中に石炭を足す必要はないのかな、と(技術職ですよね)。て、考えると短いのもわかるような。最初の形式が電化と同時期で多くても数台、たまに1台で稼動、石炭が国産出来るので戦時中でも細々と続いてたんですね。小さな鉄道が主の過渡期の存在っぽいんですが技術的には次の世代とつながってるんじゃないかな?2013/03/14
-

- 和書
- パラダイム・ロスト