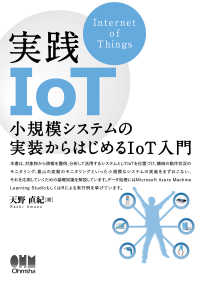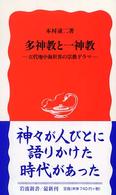内容説明
「わたし」と「われわれ」の間にある言葉。檻なのか 宇宙なのか。儚いのか 強靱なのか。短歌という詩形を抱えて旅をする。何に出会うかわからない。問いの渦と対話の中にきっと何かが始まる…
目次
1 対話は可能か
2 ジャンルを超えて
3 長い形式、短い形式
4 アートのなかの短歌
5 古典との対話
6 震災という問い
著者等紹介
川野里子[カワノサトコ]
1959年生まれ。歌人。歌集『王者の道』により若山牧水賞、『硝子の島』により小野市詩歌文学賞、『歓待』により讀賣文学賞、『ウォーターリリー』により前川佐美雄賞を受賞。評論『幻想の重量―葛原妙子の戦後短歌』により葛原妙子賞受賞。歌誌「かりん」編集委員。2023年度、2024年度、Eテレ「NHK短歌」選者(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
かふ
17
最初がギリシア哲学(プラトンが専門のような)の納富信留(哲学・西洋古典学者)が基調対話のように現在の歌壇には外部との対話(批評)がない。ソクラテスの哲学は対話の哲学だった。そしてプラトンが『国家』で詩を否定したのは、当時のギリシア悲劇の演劇で観客一丸となって感情に動かされてしまうからだという。アリストテレスになるとすでにそういう時代は過ぎているので客観的な『詩学』が書かれた。次の岩川ありさ(現代日本文学研究者)は「クィア」ということのテーマでジェンダー性の差別について。伊藤比呂美はアメリカに行った詩人。2025/08/05
さやか
1
難しい内容も多かったけれど、とても勉強になる一冊。手元に置いておきたくなった。2025/07/11
-
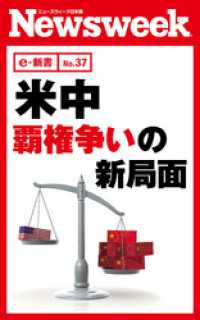
- 電子書籍
- 米中 覇権争いの新局面(ニューズウィー…