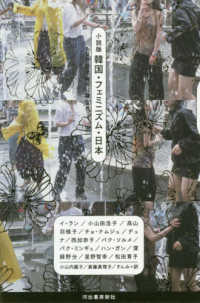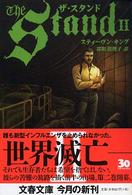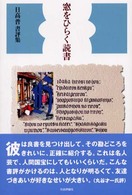出版社内容情報
岩瀬利郎[イワセトシオ]
著・文・その他
内容説明
“見ている世界”の違いがわかればともに生きるのが楽になる!あいまいな表現を使わない、視覚に訴える、「説明」と「予告」…など対応策も紹介!
目次
序章 発達障害って、なんだろう?(発達障害は病気ではなく、脳の“特性”です;注意散漫でミスを連発してしまうADHDの人 ほか)
第1章 コミュニケーションの困りごと(悪気はないのになぜか人を怒らせてしまいます;人との会話がなぜかいつも成立しません ほか)
第2章 行動の困りごと(落ち着きがなく失敗の連続。周りに心配ばかりかけてしまいます。;周りの人といつもやることがズレています。 ほか)
第3章 発達障害の取り柄と強み(特性を生かせる役割で自信を持って!;発達障害の人が持つ脳の特性が、人類を進歩させた!? ほか)
著者等紹介
岩瀬利郎[イワセトシオ]
精神科医、博士(医学)。東京国際大学医療健康学部准教授/日本医療科学大学兼任教授。埼玉石心会病院精神科部長、武蔵の森病院院長、東京国際大学人間社会学部専任教授、同大学教育研究推進機構専任教授を経て現職。精神科専門医、睡眠専門医、臨床心理士・公認心理師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
購入済の本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
読特
88
空気が読めない、会話が成立しない。優先順位がつけられず、約束時間が守れない。はまると我を忘れる。臨機応変に対応できない。夜は寝られず、朝は起きられない…ADHDは20人に1人、ASDは100人に1人。付き合いにくいと感じられる中、彼らも傷つき安さを抱えている。一方、肯定的な面もある。多動性の行動力、抜群の記憶力、発想力という強力な武器。発達障害は病ではなく特性。理解が必要。とはいえ、安易に行動の問題を発達障害に帰着するのはよくない。悪意ではないのか、矯正可能か。個性を尊重しながら生き易い社会を目指すべし。2024/01/05
k sato
59
「違う文化の人なんだ」と捉えて接するのもコツ。発達障害を持つ人の行動や心理の本質を解説した一冊。この本では、家族や職場の人が、当事者の特性を理解して手助けすることが必要だと訴えている。また、論理的ではなく感覚優先で指示をする古い企業文化が当事者を混乱させていると述べている。私見であるが、当事者が自らの特性を理解することも大事だと思う。正確で規則正しい日本の文化に適応しようとするから、当事者が苦しむのではないか。こう考えると、これらは、当事者に限った話ではない。激変する時代の生きづらさは当事者だけではない。2023/07/17
Natsuko
55
精神科を訪れ、発達障害の診断を受け、むしろほっとしている方が多いと聞く。対応法を取り上げる本も増えているが、本著はその現状と直面するドクターが、「脳の発達に特性をもつ方に見えていると思われる世界」を分かりやすく説明したうえで、本人と周囲の人々が対策を「取り合う」というスタンスであるのがいい。「ただ一方で、近年発達障害の認知が広まったが故の弊害として、多くの問題を安易に発達障害へ帰着させようとする空気がある」というあとがきにも共感。ASDとADHDの特性の解説も分かりやすく、今後大いに役立ちそう。2024/07/27
ヨンデル
54
私の家族は私を含め発達障害なので、この本は参考になりました。そもそも性格とは、生まれ持った遺伝子が生活するうえで経験することに対して適応する過程で出来上がったシステムだ、 それが性格という周りから見える形で現れたものと考えている。なので、遺伝子そのものが一人一人の働き方に偏りがあり、その上生活環境も厳密にいえば一人一人違うのでその人の持つ性格も当然変わってくる。そのことは個性だから問題ないのだが、社会での立ち位置を考えると適不適が当然出てくる。2023/06/04
TATA
51
さらっと一読する。軽めかなと思って読むととても沢山の示唆がある一冊でした。社会が成熟するという事は多くの人が不便なく生きられるということかもなと考えるとこの手の示すことがとても大事に思えます。2024/11/14