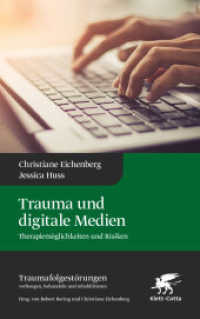内容説明
日本の学校教育が大学受験に大きく影響されている中、教育体験に基づいた現場の視点から、「国際バカロレア」について明快に解説!
目次
序章 「IB教育がやってきた」
第1章 「もう、詰め込み教育は終わりにしよう」
第2章 「IBの現場」
第3章 「IBと社会と企業」
第4章 「生きる力」
第5章 「IBのカリキュラムと実践」
第6章 「さらば受験の時代」
著者等紹介
江里口歡人[エリグチカンドウ]
1956年、愛媛県松山市に生まれる。1982年東京大学農学部卒業、1985年東京大学教育学部卒業。88年カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)教育学大学院に入学、90年教育修士課程、93年同博士課程修了、95年同大学院より教育学博士号を取得(Ph.D.)。1994年4月より玉川大学学術研究所講師。玉川学園国際教育センター副センター、同学園研修センター副センター長を経て、玉川大学教育学部教育学科准教授。玉川学園での国際バカロレア・プログラム導入に携わり、本年度玉川大学大学院教育学研究科にIB教員養成コースを立ち上げる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
だいご
5
1960年代のヨーロッパを中心に始まったIB教育が今、世界的に大きな広まりを見せている。日本でも文科省が普及させようと、通達を出している。企業側の要請で知識偏重の教育に待ったがかかった今、自ら考える力を育むIB教育は大きな広まりを見せるかもしれない。子どもたちの興味関心に沿って進められるIB教育は教師の技量が大いに求められるが、うまくいけば非常に面白いものになると感じる。来たるべき時に備えて、専門分野以外の知識も吸収し、運用する力を身につけなければならない。2020/03/27
ひつじねこ
5
バカロレア教育の具体的な事例は書かれていないが、その勘所はしっかり語られている。黒船のように扱われがちなバカロレアだが、目指す所は文科省の提言と同じだ。違うのは、その実践に対する本気度だ。綺麗事を綺麗事に留めない意識。教育はかくあるべきという姿勢がここにある。読む中で自分に足りないと思ったことがある。私は生徒の答えが的外れだった時につい是正したくなる。しかし、それよりもまず受け容れること。その後に別の考えとして答を提示すること。長い目で見るとどちらが効果的かは明らかだ。これは対人関係の全てにも言えそうだ。2017/03/08
那智@灯れ松明の火
4
非常に読みやすく、一時間半程度で読了。IB教育の概要についてroughlyに理解できた。自分はそういうやる気とか興味を伝統教育法の中で自ら作ってきたタチなので、正直「そこまで手を助けてやらなければならないのか?」と思わないところもない。あと気になるのは、生徒個人の興味のある分野をどんどん伸ばして、苦手だったり興味のない分野は強制的にやらせないことを是とする場合でも、IB教育を行う教師は苦手分野を持っていてはいけないのでは、そこは矛盾してはいないのか、ということ。自分はプレゼンは経験がないけど、(つづく)2017/02/23
Chisaka
1
国際バカロレアについての勉強本。初期的な情報をインプットできた。2024/03/23
Jinjin
1
生徒の目線から見た、この世界への疑問に真正面から答えたい、と心から思った。なんで に応えられる教員になりたい。入試制度ですったもんだしているが、根っこはこれなのではないか。なんでに向き合える余裕を社会全体で持つことができるように。問題はそこから。2019/12/18