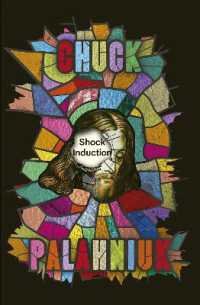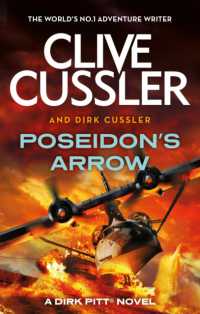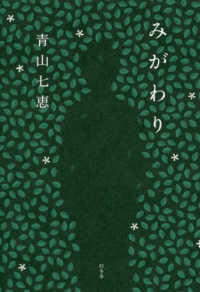- ホーム
- > 和書
- > 教育
- > 教育問題
- > いじめ・非行・不登校・引きこもり
出版社内容情報
不登校、ひきこもりに悩む親御さんへ、コミュニケーションの取り方、社会復帰に向けて立ち直らせる方法について分かりやすく解説
まえがき
第1章◆ ひきこもる子どもの本音と向き合う
まずは子どもの気持ちを理解する
A君の場合―18歳・ひきこもり期間1年
B君の場合―25歳・ひきこもり期間3年
C君の場合―30歳・ひきこもり期間4年
D君の場合―40歳・ひきこもり期間8年
ひきこもりと不登校の密接な関係
E君の場合―31歳・ひきこもり期間7年
ひきこもりの子どもは「自分は社会にいない」と感じている
子どもが将来に対する不安を持っているうちがチャンス
ひきこもりの子どもの本音は「相談する相手が欲しい」
コミュニケーションがうまくとれない
昼夜逆転、不規則な睡眠・食事
目標がない、やる気が出ない
子どもはゲームから何を得ているか?
第2章◆ ひきこもりの子どもに対する心構え
結果を求めることをやめる
回り道を怖れない
プラス思考で考える
反省・感謝する心を持つ
心の中で「1、2、3」と数える
父親と母親の役割を理解する
右と左を考える
何もしないよりも失敗した方がいい
逃げ道を作ってあげる
「イエス・ノー」をはっきりと
第3章◆【実例に学ぶ】ひきこもりから救い出す方法
F君―中学3年からひきこもり、家庭内暴力
G君―小学校からの不登校、大学1年でひきこもり
H君―高校1年から不登校、ひきこもり
I君―会社を欠勤、出社拒否からひきこもりへ
J君―中学3年に突如不登校、ひきこもりに
第4章◆ 青少年育成クラブの「心の教育」
相手を思いやる「心」
感謝・反省の「心」
強い「心」を持つ
「愛情」を持つ
【体験談】私が青少年育成クラブで学んだこと 青少年育成クラブ 専属カウンセラー 長内友樹
私はなぜゴルフを教育に取り入れたか 青少年育成クラブ 創設者 伴 茂樹
あとがき
【著者紹介】
内田直人 [うちだ・なおと]
青少年育成クラブ代表。
実践教育カウンセラー。
青少年育成クラブ代表。
昭和47年東京都生まれ。高校中退後、青少年育成クラブ創設者の伴茂樹氏に指示し、大検(現在の高卒認定)から明治大学卒業を経て、青少年育成クラブカウンセラーへ。不登校・ひきこもりなどの問題を抱える子どもたちの指導・育成に20年以上にわたって取り組む。「回り道をすることは失敗ではない」という自身の体験を元に、挫折した子どもが立ち直り、やる気を持って人生に立ち向かえるように全力を尽くしている。
ゴルフのベストスコアは69。
・青少年育成クラブWebサイト http://www.ikuseiclub.com
内容説明
ひきこもる子どもの気持ちと解決法がよくわかる!教育歴20年・1,000人以上を立ち直らせてきた専門家が教える子どもへの接し方・取り組み方。子どもの社会復帰を果たすためにどのように向き合っていくべきか?
目次
第1章 ひきこもる子どもの本音と向き合う(まずは子どもの気持ちを理解する;A君の場合―18歳・ひきこもり期間1年 ほか)
第2章 ひきこもりの子どもに対する心構え(結果を求めることをやめる;回り道を怖れない ほか)
第3章 実例に学ぶひきこもりから救い出す方法(F君―中学3年からひきこもり、家庭内暴力;G君―小学校からの不登校、大学1年でひきこもり ほか)
第4章 青少年育成クラブの「心の教育」(相手を思いやる「心」;感謝・反省の「心」 ほか)
体験談 私が青少年育成クラブで学んだこと
私はなぜゴルフを教育に取り入れたか
著者等紹介
内田直人[ウチダナオト]
青少年育成クラブ代表。実践教育カウンセラー。昭和47年東京都生まれ。高校中退後、青少年育成クラブ創設者の伴茂樹氏に師事。大検(現在の高卒認定)から明治大学卒業を経て、青少年育成クラブカウンセラーへ。不登校・ひきこもりなどの問題を抱える子どもたちの指導・育成に20年以上にわたって取り組む(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
パフちゃん@かのん変更
saga
mari
M.O.
爽快さん