出版社内容情報
時間の経緯と栄養学を結びつけて考える時間栄養学の考え方が注目されている。人間の体は1日の中で血圧や体温、ホルモンバランスが変わっていく。内臓の働きも代謝も変わるので、当然それに応じた食事の内容、仕方が変わる。そのメカニズムと具体的な方法を解説する。1日だけでなく季節など大きな時間の流れも考慮する。
目次
第1章 食べる時間が違った!?
第2章 季節に合わせた食事で体調をコントロール
第3章 こんなときはなにを食べたらいい?
第4章 動く時間が違った!?
第5章 質の高い睡眠で健康効果アップ!
第6章 最新の時間栄養学―目的とこれから
著者等紹介
蒲池桂子[カマチケイコ]
女子栄養大学栄養クリニック教授。管理栄養士。女子栄養大学栄養学部栄養学科栄養科学専攻卒業。東京慈恵会医科大学勤務を経て2000年、博士号(栄養学)を取得。2003年、女子栄養大学栄養クリニック主任に就任。栄養クリニック営業管理、生活習慣病栄養相談や企業向け栄養コンサルティングなどを行う(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Tui
17
何を?どれくらい?に「いつ?」の要素を加えた栄養学の本。人の体には25時間周期のサーカディアンリズムがあり、それに生活習慣をいかに合わせるかが大切とのことです。栄養や食生活についてもそうですが、個人的には睡眠についての項目がとても気になった。24時間周期に合わせるには、起床時に光を浴びることと、起床後1〜2時間以内に朝食を摂ることが大切だそうで。なるほど。でも毎日同じ時間に起きるのが理想とは分かっていつつ、実際なかなか難しいところ。そんな不規則な生活や勤務をしている人への処方箋も、しっかりありますよ。2017/06/05
kuma suke
8
食べる時間と生活リズム。2017/02/05
アイオライト
4
読めば読むほど田中みな実が浮かんできた。水をたくさん飲むとか、朝はフルーツでアンチエイジングとか…。やっぱり綺麗な人は生活から綺麗にしている。朝少なくすることが1番太りやすいと学んだので、頑張って朝ごはん食べるようになりました!2024/05/02
ココアにんにく
3
「時間栄養学」関連本3冊目。時計遺伝子をちゃんと理解して自分の体内時計のバランスを整えるといいことが!肥満防止や仕事の作業効率、運動効果などを上げるなど…。朝の光と食事と水分は習慣化していますが現代の生活では、特に夕食など18時まで…無理ですね。その対策法がいろいろ書かれている。タイムシフトワークの方や時差ぼけなどの対策も興味深くてメモがたくさんになりました。集中力の午前中。想像力の午後。朝の歩き。17時以降の筋トレなど時間で効果が変わってくる。病気になりやすい時間帯なども興味深いです。2018/06/06
Humbaba
2
人間の体は食べたもので作られる。ただし、食べたものがそのまま影響するというわけでもない。勿論何を食べるのかは重要だが、それと同じくらいにいつどのように食べたのかということも影響してくる。それは気を付けなければいけないことが増えるということでもあるが、それと同時に注意すれば好きなものを食べられるということでもある。しっかりとした知識を持つことで、食事がより楽しいものになってくれる。2024/11/07
-
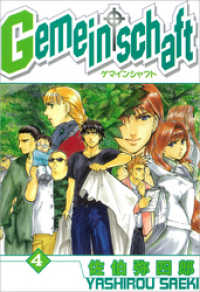
- 電子書籍
- Gemeinschaft: 4 ZER…
-
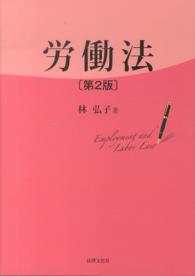
- 和書
- 労働法 (第2版)







