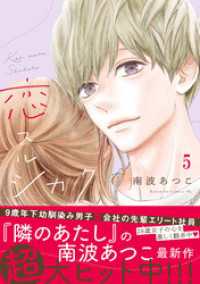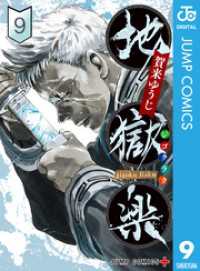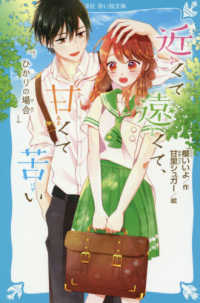目次
第1章 なぜビジネスマンがモデリングを学ぶのか(ビジネスマンとシステム開発の遠くて近い関係;モデルを利用するとは?―思考の道具としてのモデル)
第2章 ビジネス上の規則を自覚して明確化する―ビジネスモデルの作成(ビジネスのモデル化とはビジネスルールを記述すること;ビジネスモデルでは具体的に何を書くのか;概念データモデルが表現するビジネスルール)
第3章 実体関連モデル(ERモデル)を使ったデータモデルの基本的な作り方(ERモデルの基本概念;業務の説明からデータモデルで記述すべきことを抽出;ビジネスで扱うデータの構造をERモデルという形で整理する;ERモデルが示すビジネスルールを理解する;注意点:情報の鋳型と具体的な個々の情報の区別;概念データモデル定義での大原則:1つの情報は1箇所で定義)
第4章 情報の構造化の具体的な手順―データモデルを書いてみよう(ステップ0:体制を整える;ステップ1:データモデリングの材料を集める;ステップ2:材料を整理する;ステップ3:材料をもとに実体/属性/関連を定義する;ステップ4:作成したデータモデルをもとに情報を再び整理する;データモデルの完成形)
第5章 ビジネスモデルの中のデータモデル(機能をモデル化する;データのモデルと機能のモデルの関係;出来上がったビジネスモデル;定義の粒度;最後に)
著者等紹介
勝藤彰夫[カツフジアキオ]
株式会社アルゴシステム創研取締役。1957年生まれ。SI会社、外資系SI会社を経て、1995年にアルゴシステム創研(旧コムニック創研)の創設メンバーとして立ち上げから参画。その間、通信会社社内システム、金融システム、教育用ソフトウェアなど多数のシステム開発、データモデルを中心とした統合CASEツールの適用コンサルテーション、3層C/Sシステムのための設計方法論の開発と現場適用などに従事。現在アルゴシステム創研にて、DOAとオブジェクト指向を統合した自社独自の方法論の開発と現場適用、お客様の開発標準整備支援やシステム開発方法論のコンサルテーションなどを行っている。データモデルを中心としたビジネスモデリング全般に関心を持ち、調査・研究活動をしている。情報処理学会会員、JPMF(日本プロジェクトマネージメントフォーラム)会員
石ヶ森正樹[イシガモリマサキ]
株式会社アルゴシステム創研シニア・システム・コンサルタント。1961年生まれ。外資系メインフレームベンダにてメインフレーム系開発支援ツール、およびUnix用開発支援ツールの開発、適用に従事した後、外資系SI会社にてデータモデルを中心にした統合CASEツールの適用コンサルテーション、教育などに従事。これらを通して、データモデルに関するノウハウ、および、データモデルを中心にしながらシステムやビジネスをモデル化する経験を得る。その後システムのリエンジニアリングのための方法論の開発、3層C/Sシステムのための設計方法論の開発と現場適用などに従事。現在アルゴシステム創研にて、DOAとオブジェクト指向を統合した自社独自の方法論の開発と現場適用、大手顧客に対するシステム開発方法論のコンサルテーション、お客様の開発標準整備支援、教育などを行っている
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。