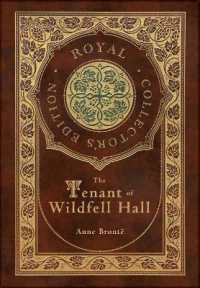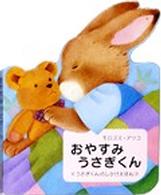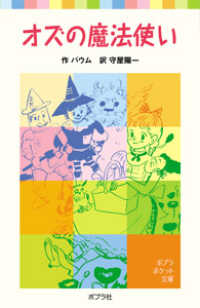内容説明
短歌とは、ご存じのように五七五七七の定型を持つ、日本独特の国民詩です。その時代々々の人々の心を伝える短詩なのです。私たちがこの現代に、一人の人間として見たり聞いたり感じたりしたことを、この詩型で切りとって作品にできたら、それだけで生きている甲斐もあろうというものです。ぜひ短歌をつくってみて下さい。
目次
「歌って」ほしい短歌
自分の視点
ことばの息づかい
色を感じさせることば
音韻の性格
軽い音、重い音
好きな音を選ぶ
発想を飛ばす
ことばが誘う連想
皮膚感覚を大事に
律調と句切れ
たおやかにつながる
題を決める
体感を生かす
色のないことばで整調する
詩のことばは明確に
ひらめきを生かす
ことばのストックを増やす
ことばの世界を広げる
特別対談「わたくし」の生のことば 穂村弘×尾崎左永子
著者等紹介
尾崎左永子[オザキサエコ]
歌人・作家。東京生れ。東京女子大学国語科卒業。著作に『源氏の恋文』(第32回日本エッセイストクラブ賞。求龍堂)、歌集に『さるびあ街』『夕霧峠』(迢空賞。砂子屋書房)ほか(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
さくら
13
おすすめしてもらった本。これぞ入門!って感じで分かりやすかった!2015/09/09
双海(ふたみ)
11
尾崎左永子流ユニークな短歌レッスン。実際に、初心者が集まって「はじめての短歌づくり」に挑戦! 「音」の性質、「リズム」など、ことばの「音楽性」からアプローチ。「この本の“カンタービレ"という題は、音楽用語で“歌うように"っていう意味ですけど、短歌には音楽性がとっても大事だということ、いつも忘れないでね」2023/10/05
真理そら
4
「昏むまで降り積む雪に紛れ行き還らぬものを過去(すぎゆき)といふ」…著者の『土曜日の歌集』の中のこの歌は大好きなので、この歌を使った音の性格の説明部分が嬉しかった。連作や題詠についての説明もわかりやすい。著者の『現代短歌入門』も分かりやすかったけれど、この本の方がより実践的で尾崎さんらしい茶目っけがある。佐藤佐太郎に師事したからなのか著者の性格なのか俗な言葉を歌に使うことを否定する姿勢が清々しい。穂村弘との対談もおもしろい、穂村弘は茂吉を超えられるだろうか。2017/12/11
みお
2
カンタービレ(歌うように)。短歌とはまさに『歌う』ものなんだ。リズムや語感の大切にという基本を改めて実感。ビギナー向けの短歌入門書としてとても勉強になります。巻末の穂村弘氏との対談も興味深い。◎2015/02/10
王天上
1
今まで読んだ入門書の中で一番実践的。好きな歌人なので創作の秘密を垣間見たようで楽しい。2018/11/23