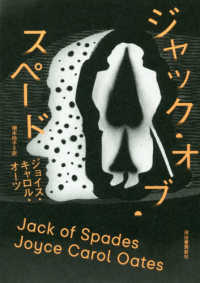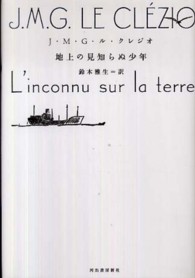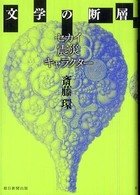内容説明
今と違う自分になりたい―それは、いつの世にあっても人類共通の夢。小説の起源はそこにこそある。嘘をつき、正体を隠し、仮面をかぶる―だからこそ面白い小説の魅力を、名うての小説読みが縦横無尽に論じる。
目次
嘘から出たまこと
人間の根源―ジョゼフ・コンラッド『闇の奥』(一九〇二)
深淵からの呼びかけ―トーマス・マン『ヴェニスに死す』(一九一二)
ジョイスのダブリン―ジェイムス・ジョイス『ダブリンの市民』(一九一四)
群衆と破壊の都―ジョン・ドス・パソス『マンハッタン乗換駅』(一九二五)
平凡のなかの濃密で豪華な生活―ヴァージニア・ウルフ『ダロウェイ夫人』(一九二五)
宙に浮いた楼閣―スコット・フィッツジェラルド『華麗なるギャツビー』(一九二五)
荒野のおおかみの変身―ヘルマン・ヘッセ『荒野のおおかみ』(一九二七)
フィクションとしてのナジャ―アンドレ・ブルトン『ナジャ』(一九二八)
悪の聖域―ウィリアム・フォークナー『サンクチュアリ』(一九三一)〔ほか〕
著者等紹介
ジョサ,マリオ・バルガス[ジョサ,マリオバルガス][Llosa,Mario Vargas]
1936年ペルーのアレキパ生まれ。サン・マルコス大学在学中から作家を志し、1958年にマドリッド、1960年パリへと居を移して創作に励む。1962年『都会と犬ども』によりビブリオテカ・ブレベ賞を受賞、さらに1966年発表の『緑の家』によって、フアン・カルロス・オネッティら有力作家を抑えてロムロ・ガジェゴス賞を受賞、以降「ラテンアメリカ文学のブーム」の花形的存在となる。1969年に大作『ラ・カテドラルでの対話』を発表した後、1970年代には創作のかたわら文学評論も手がけ、ガルシア・マルケス論やフロベール論を著した
寺尾隆吉[テラオリュウキチ]
1971年名古屋生まれ。東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了(学術博士)。メキシコのコレヒオ・デ・メヒコ大学院大学、コロンビアのカロ・イ・クエルボ研究所とアンデス大学、ベネズエラのロス・アンデス大学メリダ校など6年間にわたって、ラテンアメリカ各地で文学研究に従事。政治過程と文学創作の関係が中心テーマ。現在、フェリス女学院大学国際交流学部准教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
やいっち
三柴ゆよし
秋良
きりぱい
抹茶モナカ