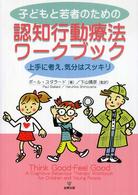出版社内容情報
朝御飯――林芙美子
大阪発見――織田作之助
コーヒー哲学序説――寺田寅彦
食 魔――岡本かの子
御萩(おはぎ)と七種粥(ななくさがゆ)――河上 肇
わが工夫せるオジヤ――坂口安吾
動物性の古い酒(炉辺漫談より)――幸田露伴
春先の好物――高村光太郎
あとがき――時代はぐるっと一回転したのである――吉田和明
作家紹介
■作家紹介■
●林芙美子(1903~1951)
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
小説家。福岡県門司市生まれ。苦学して広島県尾道市立高等女学校を大正11年に卒業。その直後、因島出身の明治大学生・岡野軍一を追って上京。翌12年岡野が帰郷し、婚約を破棄される。大震災にあい、1時両親の下に身を寄せるが翌13年には再び単身上京。近松秋江の家で2週間女中をしたのを皮切りに、工員、売り子、事務員、女給など、職業を転々としながら、詩や童話を書く。『日本詩人』『文芸戦線』に詩が掲載されたことから、詩人で新劇俳優の田辺若男を知り同棲。田辺を介して、アナーキスト詩人の萩原恭次郎、壷井繁治、岡本潤、高橋信吉、辻潤と知りあう。昭和14年田辺と別れ、詩人の野村吉哉と同棲。同 15年野村とも別れて、新宿の女給となり平林たい子と同居。同年、長野県人で画家志望の手塚緑敏と結婚。過酷な境遇にありながらも誇り高く生きた青春を日記体で綴った『放浪記』(昭和5年7月、改造社刊)がベストセラーとなる。大戦中は従軍作家として活躍。著書に『浮雲』『風琴と魚の町』『めし』などがある。
本書収載の「朝御飯」は、『林芙美子選集』(昭和12年、改造社)が初出。
● 織田作之助(1913~1947)
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
小説家。大阪市南区生玉前町生まれ。織田信長の血筋を引くといわれている。旧制三高時代に父母を相次いで亡くしたことや、友人の影響もあって文学に開眼。芸者上がりの女と駆落ちした男のことを描いた「夫婦善哉」が好評を博し、新進作家の列に加えられる。大阪を舞台に、貧しい人や薄幸の人を多く描く。大戦中は「青春の逆説」で発禁処分を受けたりもしている。戦後は太宰治、坂口安吾とともに「無頼派」と称せられたりもした。著書に『夫婦善哉』『世相』『土曜夫人』などがある。
本書収載の「大阪発見」は、その前半部分を『改造』昭和15年8月号に発表。後半部分は後日加筆したもの。
● 寺田寅彦(1878~1935)
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
物理学者、随筆家。東京都平河町生まれ。熊本の五高在学中に、夏目漱石から英語と俳句を、田丸卓郎に数学と物理学を学ぶ。この2人との出会いが寅彦の将来を決定したといっていい。明治32年9月、東京帝大理科大学物理科に進学。上京後すぐに漱石から正岡子規を紹介され、『ホトトギス』に文章を載せはじめる。大学を主席で卒業し、大学院では実験物理学を専攻。明治36年に漱石がイギリス留学から帰国すると漱石を足繁く訪ね、漱石宅で行われた文章会に高浜虚子らとともに参加する。明治37年9月、東京帝大理科大学講師に就任。同42年1月に助教授。同じ年の3月には文部省の命により宇宙物理学研究のためにドイツに留学し、同44年6月に帰国。大正5年11月に教授に任命されている。また一方、薮柑子、牛頓(にゅうとん)、寅日子、木螺山人などのペンネームで文章を発表する。大正9年11月に『中央公論』に「小さな出来事」発表以降は、吉村冬彦のペンネームを用いる。漱石の『吾輩は猫である』の登場人物・水島寒月のモデルは、五高時代の寅彦であるといわれている。著書に、『冬彦集』『薮柑子集』『続冬彦集』などがある。
本書収載の「コーヒー哲学序説」は、『経済往来』昭和8年2月号が初出。
● 岡本かの子(1889~1939)
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
歌人、仏教研究家、小説家。東京都南青山生まれ。神奈川県二子多摩川の旧家で大地主である大貫家の長女として生まれる。2歳年上の兄・雪之助が谷崎潤一郎と文学仲間だった関係で、早くから文学に目覚めた。跡見女学校に入学した頃から与謝野晶子に師事して短歌を書きはじめる。明治42年に東京美術学校の画学生・岡本一平を知り、熱烈な求愛を受けて、翌43年に結婚。同44年には太郎が生まれている。かの子は結婚後も短歌を書き続けていたが、不幸な結婚生活が機縁となりやがて宗教に目覚め、仏教研究家としても知られるようになる。小説家として知られるようになるのは、芥川龍之介をモデルにした「鶴は病みき」を昭和11年に『文学界』に発表してからのことである。このとき、かの子は47歳。49歳で死去しているので、小説家として活躍したのはほんの数年の間にすぎない。著書に、『母子叙情』『老妓抄』『生々流転』などがある。
本書収載の「食魔」は、生前未発表。創作集『鮨』(昭和16年3月、改造社)が初出。
● 河上 肇(1879~1946)
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
経済学者、思想家、詩人。山口県岩国町生まれ。東京帝大法科大学政治科卒業後まもなく、千山万水楼主人のペンネームで「社会主義評論」(『読売新聞』明治38年10月1日~12月10日)を発表し、名を知られるようになる。明治40年には『社会主義論』を、大正5年には『貧乏物語』を発表。大正8年に京大法学部教授に就任。個人雑誌『社会問題研究』を創刊する。経済学部教授に転じ、昭和3年に京大を去るまでに、『経済学大網』(昭和3年刊)、『第二貧乏物語』(昭和5年刊)、『資本論入門』(昭和7年刊)を書きあげている。真理の前には身を捨ててもいいという信念の下、ブルジョワ経済学からマルクス主義経済学へと転身をはかり、昭和7年には非合法下の共産党に入党。翌8年検挙、下獄。同12年まで刑務所にあった。出獄後、昭和18年までの間に、自らの波乱の人生を省みるとともに退潮期の革命運動を赤裸々に描いた『自叙伝』4巻(昭和22年5月~同23年3月刊)を書きあげている。『自叙伝』は思想史の資料としても第一級の文献との評価が高い。他、詩歌集として『雑草集』『雑草集其二』『旅人』などがある。
本書収録の「御萩と七草粥」は、『思い出(断片の部・抄出)』(昭和21年10月、月曜書房)に収められたのが初出。太平洋戦争中に、発表の当てもなく書かれたものの1篇である。
● 坂口安吾(1906~1955)
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
小説家。新潟市西大畑町生まれ。坂口家は代々阿賀野川流域の大安寺村に住した旧家で、大地主であったが、安吾が生まれた頃にはすでに傾いていた。中学卒業後に小学校の代用教員になるが、求道の厳しさに対する憧れから翌大正15年には東洋大学印度哲学科に入学。悟りを開こうと4時間の睡眠時間で、哲学書や宗教書を読む生活を続けるが精神衰弱に陥る。それを、梵語、パーリ語、チベット語、フランス語の勉強をすることによって克服したという。大学に通うかたわら通いはじめたアテネ・フランセの友人たちと同人誌『言葉』(後、『青い馬』と改題)を発刊。この雑誌に発表した「風博士」が牧野信一に、「黒谷村」が島崎藤村と宇野浩二に激賞され、文壇で注目されるようになる。昭和6年、牧野信一、小林秀雄、井伏鱒二らの『文科』の同人となる。その後、田村泰次郎らの『桜』や宇野千代、三好達治らの『文体』に作品を発表し、同15年には大井広介、平野謙、檀一雄らの『現代文学』の同人となる。戦後に発表された「堕落論」は、混乱と背徳の果てに人間回復を待望するものとして、虚脱状態にあった戦後の知識人に大きな衝撃を与えた。太宰治、織田作之助らとともに「無頼派」の名で呼ばれるようになる。昭和24年、睡眠薬と覚醒剤の中毒症状が高じて、東大神経科に入院。同28年、国税庁と税金滞納をめぐって対決したり、競輪不正事件で自転車振興会を相手に闘うなど、新聞社会面を賑わすようなこともあった。著書に、『女体』『桜の森の満開の下』『不連続殺人事件』などがある。
本書収載の「わが工夫せるオジヤ」は、『美しい暮らしの手帳』11号(昭和26年1月1日発行)が初出。
● 幸田露伴(1867~1947)
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
小説家、劇作家。江戸下谷三枚橋横町生まれ。明治12年、一ツ橋の東京府第1中学校に入学するが翌年に中退。同14年、銀座3丁目の東京英学校(現・青山大学)に入学したがこれも中退。湯島聖堂の東京図書館に通いつめ、古書を乱読し、後年の博識の基礎を築いた。この頃、坪内逍遥や尾崎紅葉との交流がはじまった。明治22年、「風流仏」が世に認められる。同年12月、読売新聞社に入社。明治24年、愚鈍な大工・十兵衛が塔の建立を見事に果たす「五重塔」を発表。同29年3月より、「脱天子」の名で、森鴎外の主宰する『めざまし草』の新作小説を合評する欄「三人冗語」に、鴎外、斎藤緑雨とともに批評を載せるようになる。明治30年以降は活動の重点を、小説を書くことから評論、随筆を書くことに、また校訂、編著の方に移しはじめる。明治40年代からは史伝類に手を染めるようになる。露伴は尾崎紅葉とともに並び称せられる明治期を代表する小説家である。著書に、『天うつ浪』『幽秘記』『幻談』などがある。
本書収載の「動物性の古い酒」は「炉辺漫談」中の1篇である。「炉辺漫談」は、『東京日日新聞』昭和6年1月3日号~11日号まで連載された。「炉辺漫談」中には、他に「鮫の袴」「魂魄のむき」「ふしぎ」「農家の生くる道」が収められている。
● 高村光太郎(1883~1956)
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
彫刻家、詩人。東京都下谷生まれ。東京美術学校に通っていた明治33年に与謝野鉄幹の新詩社に入社。明治39年2月にアメリカに旅立つまで、『明星』に短歌、感想文、戯曲、詩、翻訳を載せている。ニューヨーク、ロンドン、パリに滞在し、明治42年6月に帰国する。本気で詩を書くようになったのは、明治 44年1月『スバル』に「失はれたるモナ・リザ」「根付の国」など6篇を発表した頃からである。その頃、長沼智恵子を知る。大正3年10月に詩集『道程』を自費出版する。智恵子没後の昭和16年8月、智恵子について歌った詩や散文を集めて詩集『智恵子抄』を出版。昭和15年中央協力会議議員、同17年文学報国会詩部会会長に就任。同20年4月アトリエが焼け、宮沢賢治の縁故を頼って岩手県花巻町に疎開。終戦後も帰らず、近郊の太田村山口の小屋に住んで農耕自炊の生活を続けた。著書に、『印象主義の思想と芸術』『ロダンの言葉』『美について』などがある。
本書収載の「春さきの好物」は、昭和15年5月頃書かれ、『某月某日』(昭和18年4月、龍星閣)、『獨居自炊』(昭和26年6月、龍星閣)などに収められた。
Public Domain(著作権が公衆のもの)になった名作のテーマ別アンソロジー。名著入門、再読の手引として巻末に作家紹介を付けた。本文は14Qと大き目の活字を使用し、新字・新仮名遣いで表記した。難読漢字はもとより、送りがなが本則でない漢字にもフリガナを振ってある。現代では理解しにくい歴史事項や人名には文中に割り注で説明を加え、中学生から団塊の世代まで幅広い世代に楽しんでいただけるよう工夫した。
内容説明
著作権が公衆のものになった名作のテーマ別アンソロジー。食をテーマに8人の作家の作品を収録。
著者等紹介
吉田和明[ヨシダカズアキ]
評論家・コラムニスト。千葉県館山市生まれ。法政大学経済学部卒業。東京工業大学社会理工学研究科博士課程修了。80年代に綜合評論誌『テーゼ』を創刊、主宰。86年より、日本ジャーナリスト専門学校講師。また、この間、大学やカルチャーセンターなどの講師も務める。評論執筆の傍ら、『北海道新聞』など地方紙を中心に、コラム、書評、エッセイなど400本以上を執筆する
新田準[ニッタジュン]
1947年生まれ。上智大学外国語学部ロシア語学科卒。卒業後商社勤め10年間のあいだに、ウイーン駐在東欧巡回員などを経験。凱風社設立メンバー(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。