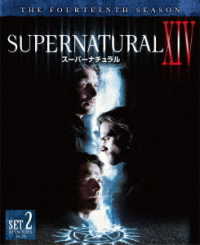出版社内容情報
「労働にはもともと、苦役の面と、生きる歓びの面との二つがあって、仕事の内容、状態、本人の身分や階級、資格、能力、時代の気風、などなどの条件でそれらがはっきりと、あるいは微妙に入りまじる。……働くということが単に生活費を得るという以上のものであるためには何が必要か。どうしたら働くことが生きる歓びになり得るのか」――戦前から最近までの映画に表れた主人公の生き方と著者の独学人生から導き出された、働くことの意味と労働の誇りを考える。
なぜ映画に労働を見ようとするのか
仕事への愛着●『秀子の車掌さん』
民衆の誇り●『あゝ野麦峠』と山本茂美
社会的責任感●『生命の冠』
共働き●『看護婦のオヤジがんばる』
結婚と女性の就労●『クレーマー、クレーマー』
サラリーマン●〈三等重役〉シリーズから〈社長〉シリーズへ
天職 その1●『父ありき』
戦後民主主義●『東京五人男』
肉体労働●『わが町』
民族差別 その1●『どたんば』と朝鮮人差別
有無相通ず●〈男はつらいよ〉シリーズ
下請企業●『アッシイたちの街』
「労働者」像●『土佐の一本釣り』『青春の門』
公害●『東京クロム砂漠』
知的労働●中国映画と文化大革命
労働の神聖化●『意志の勝利』
民族差別 その2●『蜃気楼の国のアリ』と出稼ぎ労働者
単調な労働と生甲斐●『生きる』『クレールの刺』『月曜日に乾杯!』
若者の筋肉労働●『深呼吸の必要』
楽しさ、面白さ●〈釣りバカ日誌〉シリーズ
天職 その2●『鉄道員(ぽっぽや)』と高倉健
自治の力●『掘るまいか』
仕事の貴賤●椎名麟三の小説をめぐって
一人前になるということ
◆はじめに
かつて、エジプトのピラミッドは奴隷労働によって作られたものだと考えられていた。あんなバカでかいものは絶対的な権力を持つ王様の命令による奴隷労働でなければできるものではないように思われ、当然のことのようにそう思われてきたわけだ。しかし近年研究がすすんで、当時の労働者の出勤簿などが発掘され、二日酔いでサボることも認られていたなどと分って、あれは案外、公共社会事業的な性格もあった仕事で、人々は喜んでそれに参加したのではないか、という説も現われるようになった。
労働にはもともと、苦役の面と、生きる歓びの面との二つがあって、仕事の内容、状態、本人の身分や階級、資格、能力、時代の気風、などなどの条件でそれらがはっきりと、あるいは微妙に入りまじる。苦役以外の何物でもない労働もあれば面白くてたまらないような仕事もある。もちろん大部分はその中間にある。そこに本人の適性や主観も条件として加わるからどれがいいの悪いのといちがいには言えない。
労働についてのイデオロギーも、支配者側は、職業に貴賤はないのだからみんな自分の仕事に満足して喜んで働け、と言いたがる。他方近代のマルクス主義系の思想家たちや芸術家は、資本主義社会では労働はどうしても苦役になりやすいと主張して、労働の歓びは社会主義社会にしかあり得ないと強調した。しかし現実には社会主義社会こそが強制労働などを土台にしてかろうじて成り立った場合が多かったことが明らかになり、その多くが崩壊してしまった。
しかし彼らが主張した、労働を人間的なものにしてゆこうという願いを資本主義社会が解決したとも言えない。社会全体を豊かにしたことで資本主義先進工業諸国は労働を比較的に楽なものにした。しかしそれはじつは、人間を搾取するかわりに地球の資源をより効果的かつ徹底的に搾取する手段をどんどん開発したことの結果である。かくして地球は破滅に向ってまっしぐらと見える。なんとかしなければならない。この大問題を解決する確かな方法なんて分るはずもないが、少なくともその鍵のひとつは、やたら資源の浪費につき進む横着を止めて肉体労働の意義を見直すといったところにあると思う。
なんだか大げさな話になってしまったが、どんな労働なら苦役で、どんな労働なら歓びであり得るか、いまやあらためて考えてみる時期であると思う。
この本におさめたエッセイの多くは、一九八〇年代のはじめに日本労働組合総評議会(通称・総評)の機関誌『月刊総評』に書いたものである。労働組合の雑誌だから、映画を手掛りにして労働の意味について考えてみようとしたのである。これを凱風社が『スクリーン労働論』という本にまとめて一九八四年に刊行して下さった。だから扱っている映画にはいまでは忘れられているような作品もあるが、当時は働くということの意味を考えさせてくれるような作品が多かったと思う。それらのうち、いま読み直してさらに考えてみたいと思った文章を選んで加筆したり、さらにそのごに見た映画で新しい観点を見出して書いたりして新たにこの本をまとめた。映画と直接関係はないが、働くということについて考えた他のエッセイも加えた。
「一人前になるということ」は私の旧著『いかに学ぶべきか』(大和出版、一九七三)に収めた「私の独学と職業」を大幅に書き直したものであり、「仕事の貴賤」はおなじく『苦労人の文学』(千曲秀版社、一九七八)に収めた「椎名麟三論」に加筆したものである。私は映画評論家であるが、働くこと、学ぶことなどにはつねに関心があって、折にふれ考えつづけてきた。
働くということが単に生活費を得るという以上のものであるためには何が必要か。どうしたら働くことが生きる歓びになり得るのか。それが問題だ。
◆なぜ映画に労働を見ようとするのか
映画というものは、原則として、人が労働でくたびれたあとで、その憂さばらしに見にいくものである。すでに労働でうんざりしている人は、映画館のなかでまで、労働を見ようとは思わない。したがって、映画のなかでは労働する人間の姿は滅多に描かれないし、描かれてもごく表面的でしかないことが普通である。社会主義国では労働は喜びであるというタテマエになっていたから、比較的よく、労働が描かれるが、社会主義の弱点が露呈してこのタテマエも怪しくなった。
映画は、恋愛や戦争や少年非行や暴力団の活動や家庭の幸福は熱心に描くが、原則として、労働を描くことには熱心ではない。ときに熱心になるときがあると、それは、革命や軍国主義で、権力者が民衆を猛烈に働かせる必要が生じているばあいの宣伝のためであったりして、ロクなことがない。労働の尊さ、といったことを強調する映画が出てくる時代は良くない時代であることが多いのである。
映画と労働の関係が大雑把に言ってそういうものであるとすると、そんな映画のなかから、労働について触れた部分をとりあげて、それについて考えるというようなことは虚しいことのように思える。そこからはたして、どれだけ実りのある考察が得られるのであろう。映画を論ずるならばやはり、映画とセックスとか、映画と暴力とか、映画と遊び、といったテーマのほうが、少なくとも材料は豊富だし、作者たちが大いに乗ってつくっている卓抜な表現も多い。
が、しかし私は、天邪鬼めくが、映画にとって不得手な領域であるからこそ、映画に描かれた労働について語りたい。映画が可能なかぎり人間の活動を総合的に表現する文化手段である以上、苦手であってもこのテーマを避けて通ることはできないし、苦手であればあるほど、なぜ苦手かということをつうじて、そこにある、複雑で解き難い労働の問題点が見えてくると思うからである。
* * *
私の労働経験は、太平洋戦争中、小学校高等科二年のときに、学童動員で鉄工所で鋳型づくりを半年ほどやったことに始まる。小学校を卒業してから同じ鉄工所の造船部で鋲打ち工の見習いを一カ月ほどして海軍の少年兵に行き、すぐ敗戦になって復員してから、こんどはその鉄工所の車輛部の木工の見習いを四カ月ぐらいやった。その後、国鉄(現JR)の鉄道教習所で三年間学び、卒業して国鉄の現場の電気関係の作業場に三カ月ほど勤務したところで行政整理でクビになった。一九四九年、大量失業時代である。職業安定所の前の長い行列に並ぶ経験をいやというほどした。電気工事店の住込みの店員もしたが、一カ月でネをあげた。
その後、日本電信電話公社(現NTT)の電話機修理工場に、定員外の臨時雇という名目で雇われ、数年、その不安定な身分でいてやがて正式に採用された。ここでは七年間、無事につとめて、電話機の修理工としてはベテランになった。ここで働いている間に映画雑誌などにエッセイの投稿をつづけ、それが認められて、二十五歳頃に雑誌編集者、文筆業に転じた。
私は労働者であったが、労働者としては長い間、半人前であった。修業時代が半人前であるのは当然であるが、何度も修業時代に挫折し、そのたびに修業をやり直したので、労働者としていつになったら一人前になれるのだろうという不安と無力感に長いこととらわれつづけていた。一方で私は文筆に志があり、労働に打ち込もうという気持は乏しかった。自分は立派な労働者ではないという劣等感と、辛い労働から逃避するために文筆の道に逃げ込んできたのではないかという、一種の後ろめたさが私にはあった。もちろん、文章を書くことだってある種の厳しい労働ではあるのだが、私は要するに、工場などでの地道な仕事を嫌って、もっと自分にとって面白い仕事を選んだのだ。
しかし私が文筆業に転じることができたのは、じつに多くの偶然に左右された結果であり、その偶然がひとつでも欠けていたら、私はやはり、電話機の修理工をしていたであろう。いや、私が電信電話公社を去ってから電話機というものはもう修理の必要のないものになり、修理するくらいなら丸ごと取り替えたほうが早いという状況になって、いまでは電話機修理工は必要がなくなっているらしい。公社に残っていたら、その意味でまた職工としての深刻な挫折を感じないわけにはゆかなかったのではなかろうか。やっと電話機修理工としてはベテランになったところで、こんどはその職種自体がなくなったとしたら私はどうしていただろう。クビにはならないにしても、気持よく働くことははたしてできただろうか。
* * *
これまで、労働問題と言えば、主として経済的なことであった。現在でも、零細な下請企業や臨時雇の労働者たちにとって、それは重大な問題に違いない。しかしいま、労働の問題はやや違ったものになりつつある。ただ賃金が良ければ良いというだけではなくて、気持よく働ける仕事であるかどうか、意義の感じられる仕事であるかどうか、仕事が面白いかどうか、ということが、労働の問題点になりつつある。技術革新と管理社会化の進行は、人々の労働の質を急激に変化させつつあるが、その結果が人々の労働をより楽しいものにするか、より退屈なものにするか、それが大問題であろう。そこで人々は、労働のありかたについて、いっそう真剣に考えざるを得なくなる。
現在から将来にかけて、人々はしだいに、賃金が安いからストライキをするというより、仕事がつまらないから、仕事に意義が感じられないからサボるというふうに変ってゆくのではないか。若者のフリーター化やニート化とはそういうことではないか。
人間、誰しも、自分自身に正当な誇りを持たないわけにはゆかない。私は少年時代、青年時代に、労働者であることの誇りを模索したが、それは、そう手軽には手に入るものではなかった。労働者にとって、労働の何が誇りとなり得るか。それはいまでも、私にとって大きな課題である。労働についての、まやかしの誇りはたくさんある。まやかしの誇りを与えようとする者たちに対しては憎しみをさえ感じる。しかし、にもかかわらず、誇りをもって働きたい、と、私は若いころに切に思った。その気持はまだ、私の心のなかに宿題として残っている。
私はいま、知識労働者というか、頭脳労働者というか、そういうものであるわけだが、知識労働と肉体労働とがいかにして調和よく存在し得るか、という問題がまた、重要である。中国の文化大革命はこれを極端に暴力的なやり方で解決しようとして元も子もなくしたが、問題はまだ提起されたばかりであり、違うかたちで繰り返し問題は提起されつづけることであろう。
* * *
家事労働を女にだけ押しつけるのはいけない、という主張は、近年、世界的に女性たちから持ち出され、生活の様相を大きく変える要素になったし、この点に関しては、映画もしきりに取り扱っている。男と女が、互いに相手の労働をどう理解するかという点において、映画が果たす役割は大きいと思う。世界的に言えば、女性の映画監督の進出がいちじるしく、女性の主張の多くがそこから出てきている。
その点、日本の映画界は、女性の映画監督がきわめて少ないということで世界的にきわだっている。テレビでも女性のディレクターは非常に少ない。ただ希望は、テレビの脚本家には女性の進出が目覚ましく、しかも大衆的な人気のある人が多いことである。そこらがひとつの有力な突破口となって、女性の労働の問題についての女の立場の発言も増すだろう。
かつてマルクスが言った「万国の労働者よ団結せよ!」というスローガンは、これまでのところ、ほとんど絵空事でしかなかったが、いまようやく、労働者の視野も国際的になりかけてきているのではないか。
とくに、南北問題を労働者がどう考えるかが、歴史の進路に大きくかかわってくる。労働者はようやく、自分の労働のあり方を考えるのにも世界情勢を考慮に入れなければならない段階に達していると思う。
以上のような問題はいずれも、考えをすすめるうえでさまざまな感情的な事柄にぶつかるものである。そこに映画のような大衆文化の果たすべき役割も出てくるし、それは決して小さなものではないと思うのである。
「額に汗する労働は愚か者の所行」だろうか。映画に描かれた主人公の生き方と著者の独学人生から導き出された、働くことの意味と労働の誇りを考える。
内容説明
働かない…、働きたくても働けない…、働いても面白くない―「少子化社会」「下流社会」化と言われる時代にあっても、労働は一人ひとりの人生に直面する大問題。なぜ働くことは必要なのか―この古くて新しい課題の答えはなかなか見つからない。ちょっと立ち止まってこの大問題をみんなで考えてみよう。
目次
仕事への愛着―『秀子の車掌さん』
民衆の誇り―『あゝ野麦峠』と山本茂美
社会的責任感―『生命の冠』
共働き―『看護婦のオヤジがんばる』
結婚と女性の就労―『クレーマー、クレーマー』
サラリーマン―「三等重役」シリーズから「社長」シリーズへ
天職その1―『父ありき』
戦後民主主義―『東京五人男』
肉体労働―『わが町』
民族差別その1―『どたんば』と朝鮮人差別〔ほか〕
著者等紹介
佐藤忠男[サトウタダオ]
1930年新潟県に生まれる。国鉄職員、電電公社員、『映画評論』『思想の科学』編集長を経て、文化、教育全般にわたる幅広い評論活動を展開。映画評論家。日本映画学校校長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
-
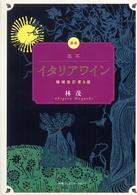
- 和書
- 最新基本イタリアワイン