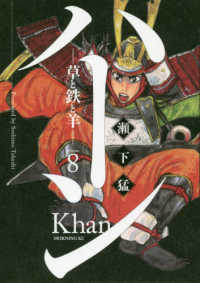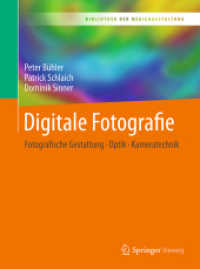出版社内容情報
新選組を生んだ「多摩」の地はかつて他国の侵略には鍬を剣に持ち替え、一致して闘うもののふの郷(さと)であった。五日市憲法や自由民権運動に代表されるように、培われてきた自主・自治の精神は中央政権の支配に屈した日清戦争前夜まで受け継がれていく。特に幕末維新期、多摩人が夢見たのは共和政体の実現ではなかったのか。三谷幸喜「新選組」像等に見られる立身出世願望説を批判的に再検証し、壮大な多摩人の「闘い」を発掘した歴史ノンフィクション。
はじめに
本書関連事項年表
●第一章
天然理心流を生んだ武士の郷
多摩の歴史は侍の歴史
甲州一揆
世直し江川大明神
多摩川の取水堰争い
岡引・八五郎の活躍
彦五郎の手習い
八王子千人同心
江川代官、日野宿へ
彦五郎の仮祝言
洪水に見舞われた歳三の生家
宮川勝五郎の入門
佐藤邸炎上
●第二章
江川担庵の業績と多摩人の自立精神
勝五郎、宮川家に養子に入る
江川担庵、種痘を実施
蘭方医ネットワーク
薬売りになった歳三
ペリー艦隊の来航
御台場の建設着工
佐藤道場の開設
安政の大地震
担庵、総蔵を走らす
義兄弟の契り
開国に洗われる多摩
大献額奉納式典と野試合
剣士たちの恋と病
熱く国事を語る
●第三章
武相農兵隊の結成と近藤勇の信念
浪士組参加決定の内幕
将軍上洛
江戸大変、武相騒乱
多摩のスポンサー
新選組の誕生
武相農兵隊の結成
多摩と京都の通信
禁門の変、多摩を走らす
天狗党、関東を駆ける
近藤勇の一時帰還
●第四章
明治元年は瓦解元年
支配替えの阻止
第二次長州征伐
武州世直し一揆の勃発
歳
●はじめに
二〇〇四年のNHK大河ドラマは三谷幸喜脚本による『新選組』だった。主役の近藤勇役に人気の香取慎吾を起用するなど、三谷の手腕は冴え渡り、ストーリーも若者受けを狙って大胆に脚色されている。史実をトレースするものではなかったとはいえ、まずまず、好評を博したことはめでたいことである。ふつう、大河ドラマともなれば県を挙げてのお祭り騒ぎになるものなのであるが、今回、東京都は一切何もしてはいない。近藤勇のふるさと・調布と土方歳三のふるさと日野が、競うように町おこしを狙ったに過ぎない。多摩という地方は統一した行政単位をなしていないので、個々の自治体がばらばらに取り組むほかはないのである。東京都は多摩全体の問題に関心など持ってはいない。
ドラマのおかげで「多摩」という地名の存在が広く知られるようになった。一年を通して「多摩の百姓」という言葉が何度も繰り返されたからである。かつて、日本最大の面積と結束力を誇った多摩郡、武蔵の国の中心であった多摩も、人々の意識の中で地盤沈下を起こし、忘れ去られようとしていたといっていい。分割されて三多摩になってからも、調布市を含む北多摩郡、日野市を含む南多摩郡は全域が市られた調布、日野の町おこしも、その上塗りの域を出なかった。
多摩は元来、闘う百姓の郷、もののふの郷である。ふだんは鍬を握り、他国に侵されようとするときは一致して剣に持ち替えた。しかも多摩は、中心地もリーダーも持たずに、ネットワークとしてこの団結を維持した。日本の歴史の中でもきわめて貴重な自主と自治の郷なのである。
幕末、多摩の百姓の固有の歴史が再び目覚めた。欧米の脅威に対する自衛意識と、その能力の存在確認と限界確認。そうしたものを通して、多摩はこの国の未来像を引き寄せることになる。自らが主人公であるという自信、それが多摩の幕末維新を染め上げた。新選組とは、そうした流れの中で産み落とされた確かな傍流に他ならない。本流は維新後もとうとうと流れ続け、自由民権運動へと受け継がれる。神奈川壮士、三多摩壮士である。
自主と自治、自由と民権、この先に多摩が夢見たものは共和政体、共和国であろう。中心地もなくリーダーもない。中央集権とは正反対のネットワークである。多くの人々が対等にひざ突き合わせて議論をし、統一した方針を導き出す。民主主義のこのプロセスを、多摩は歴史的に得意としてきた。本書はそれを明らか
新選組を生んだ多摩とはどういう地だったのか。幕末維新期、多摩人は天皇制政権に抗って共和政体の実現を夢見たのではないか。この地が放ち続けた「輝き」をすくい上げた反骨の書。
内容説明
新選組を生んだ多摩とはどういう地だったのか。幕末維新期、多摩人は共和政体の実現を夢見たのでは?自治・自由を求めた人びとがはなつ輝きをすくい上げた歴史ノンフィクション。
目次
第1章 天然理心流が生んだ武士の郷(多摩の歴史は侍の歴史;甲州一揆 ほか)
第2章 江川担庵の業績と多摩人の自立精神(勝五郎、宮川家に養子に入る;江川担庵、種痘を実施 ほか)
第3章 武相農兵隊の結成と近藤勇の信念(浪士組参加決定の内幕;将軍上洛 ほか)
第4章 明治元年は瓦解元年(支配替えの阻止;第二次長州征伐 ほか)
第5章 民権から国権へ―未完の「多摩共和国」(多摩分割と御門訴事件;郷学校の発足と廃藩置県 ほか)
著者等紹介
佐藤文明[サトウブンメイ]
フリーランスライター・戸籍研究者。1948年、東京都南多摩郡日野町生まれ。日野・上佐藤の出身で八王子育ち。八王子千人同心に興味を持ち、高校時代から研究を開始、高校は都立立川高校(著者は多摩立を自称)。法政大学在学中に東京都の職員(総務部総務課)となり、新宿区役所に希望転属。戸籍研究者としての第一歩を踏み出す。1972年より現職。79年、「“私生子”差別をなくす会」を結成、婚外子差別の廃止を目指すとともに、82年には「韓さんの指紋押捺拒否を支える会」を結成。指紋制度の廃止と取り組む。現在は「女性と天皇制研究会」「自由民権21」メンバー。ライターとして行政事件、冤罪事件、戦時動員、多摩の幕末維新などを追究の基本テーマとしている
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
えみ
り こ む ん
ring8789