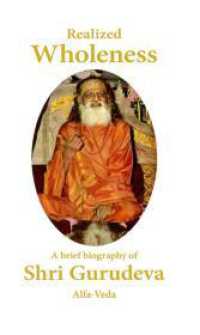出版社内容情報
文化庁の在外研修員として映画作家が訪ねたのはドキュメンタリー映画の発祥の地・イギリスのロンドン。ヒマにまかせて夜な夜な映画館をハシゴする毎日。ところが何故か、目蓋が重くなることが多い。どうしてだろう。そうだ、多分間違いなく、それは優れた映画だからだと納得。ロンドン映画生活を謳歌する中で、〈コモンセンス〉という名のルールがはらむ危うさと摩訶不思議さをフレデリック・ワイズマンばりに解剖しつつ、微睡むままに書き留めた悪口満載の辛口エッセイ。
まえがき
第1章 塩 SALT
第2章 水道屋 PLUMBER
第3章 犬 DOG
第4章 雨 SHOWER
第5章 ラウンドアバウト ROUNDABOUT
第6章 地下鉄 TUBE
第7章 テレビ TELEVISION
第8章 学校 SCHOOL
第9章 シネマ CINEMA
あとがき
●まえがき
私は昔から、映画を見るとすぐ眠くなる悪い癖がある。映画館のシートにもたれて、開演のブザーが鳴り、照明が落とされて辺りが暗闇に包まれると、困ったことに、途端に眠くなる。上映作品が、どうしても見たいと思っていた好きな映画だと、なお更だ。スクリーン上の画面に気持ち良く身を任せているうちに、気が付くとついウトウトしてしまう。そんな時、これは映画の中の出来事なのか、それとも自分が夢見心地の世界に遊んでいるだけなのか、分からなくなってしまう。そんな妄想癖が私にはある。
ただ、私も一応、映画監督の端くれである。その上、求めに応じて書いた映画批評のまね事では、つい筆がすべって罵詈雑言を書き散らしてきた。だから、本当は映画を見るたびについウトウトとしてしまうなどとは、口が裂けても言えない。そう頑に思い込んで、いつも眠くなるのを懸命に我慢してきた。
しかし、待てよ、と最近思い直すようになった。ウトウトするのは、決して観客の側の怠慢ばかりではない。つまらない映画なら、腹立たしいやら、口惜しいやらで、とても眠くなるどころではない。むしろ、金返せと叫びたくなるくらいではないか。いい映画だから眠くなる直りとも受け取られかねないが、これが最近の私の批評基準である。それはまた、眠くなるドキュメンタリー映画をいつまでたっても撮ることのできない私の、密かな目標でもある。
二〇〇二年八月から一年間、イギリスで暮らした。文化庁派遣芸術家在外研修員として、BFI(イギリス映画機構)に所属して、英国ドキュメンタリー史を学ぶためである。しかし、実際の研修の内実は、一年の長期休暇をもらってブラブラと物見遊山を繰り返すばかりの自堕落な日々であった。私は、ヒマにまかせて、ロンドン市内の映画館をハシゴする毎日。この映画館の暗闇で、映画を見ながら、いつもついウトウトとしてしまう。本書のタイトル『まどろみのロンドン』は、そんな私の情けない状態をひと言で言い表したものである。この微睡みの中で私の脳裏に出没した妄想の数々がこのエッセイ集の核となった。誤解ないように書き加えておくと、微睡んでいるのはロンドンという都市でも、そこに暮らすイギリス人でもない。この都市に暮らした私の頭がいつも微睡んでいたのである。
この文化庁の在外研修は、実に有り難い制度である。月に一度、簡単な報告書を書く以外には、なんの制約もない。ただ、研修先の> イギリスに暮らしはじめて、いざ写真エッセイを書こうと原稿用紙に向かうと、冷や汗ばかりが出た。ただヒマにまかせてブラブラしているばかりの毎日では、何も書くことがない。肝心の映画研修の方は、映画館の暗闇に紛れてウトウトしっぱなしで、なんの成果らしい成果は上がらない。そのため、苦肉の策ではあるが、日本というコンテキストを離れて感じた由無し事を書くように方向転換を計った。だが、実際はイギリスの映画事情や文化紹介を書こうにも、書くことがなかっただけの話である。
もともと私の在外研修は、イギリスでなくてもよかったのだ。どうしてもロンドンでなければいけない理由は何ひとつない。むしろロンドンを選んだ理由は、消去法で残ったのである。映画の都パリもいいが、フランス語がひとつも分からないし、ニューヨークは子供たちと一緒だとなんとなく気が引けるし、そんな可能性をひとつひとつ消していったら、ロンドンが残ったに過ぎない。
エッセイを書きながら意識していたのは、フレデリック・ワイズマンの映画のことであった。『チチカット・フォーリーズ』(一九六七年)以来、三〇年以上にわたって三〇本以上のドキュメンタリー映画を撮り続けていに掲げた普通名詞にまつわるあれこれを考えていると、自然に映画の話題になった。これは、私も映画監督の端くれであるという職業倫理によるものか、所詮映画のことしか知らないという無知の証拠か、微妙なところである。最近の日本のドキュメンタリーの閉塞状況の原因のひとつに、映画作家が映画のことしか知らない無教養が指摘されることがある。映画のことも知らずに映画を作れる訳はないが、映画のことしか知らないようでは、たいした映画はできない。
私が本書で試みたことは、些細な日常をとりまく、映画以外の出来事の奥行きを見つめようとしたものだったはずだ。しかし、その目論見も最終章「シネマ」で、結局は映画のことに戻ってきて、元の木阿弥になってしまった。
願わくば、本書をひもとかれた賢明な読者の方々が、私の微睡んだ脳裏に去来する妄想の中から、映画では表現できない出来事の奥行きの一端を味わっていただければ望外の喜びである。かくいう私は、映画のことも分からないおのが不明を恥じながら、新作『阿賀の記憶』の編集で、またぞろ暗礁に乗り上げて四苦八苦を続けている。残念なことに映画作品は、微睡みや妄想の中からは決して生まれてこないのである。
『ドキュメンタリー映画の地平』『映画が始まるところ』を著した映画作家の、旅には全く役に立たないロンドン滞在記。優れた映画に微睡みながら考えた由無し事がドキュメンタリーの本質まで迫る。
内容説明
妄想は、ヒマにまかせて夜な夜なハシゴする映画館の暗闇から始まった。イギリスに潜む“コモンセンス”という名のルールの危うさと摩訶不思議さの内実とは?ドキュメンタリー映画作家が、筆のおもむくまま半覚醒状態で書き留めた悪口満載の辛口エッセイ。
目次
第1章 塩
第2章 水道屋
第3章 犬
第4章 雨
第5章 ラウンドアバウト
第6章 地下鉄
第7章 テレビ
第8章 学校
第9章 シネマ
著者等紹介
佐藤真[サトウマコト]
1957年青森県弘前市生まれ。千葉県松戸市のマンモス団地で物心がつき、東京都練馬区石神井で育つ。東京大学文学部哲学科卒業。在学中より『無辜なる海―1982・水俣―』(香取直孝)の助監督に参加。水俣の漁村に暮らして人生に悩む。この映画の自主上映の旅先で、阿賀野川とそこに暮らす人々と出会い、この地で映画を作ることを決意する。各務洋一監督に私淑した後、89年からスタッフ7人と阿賀野川の川筋で共同生活を続け、92年に『阿賀に生きる』を完成。ニョン映画祭銀賞、芸術選奨新人賞など、国内外で高い評価を受ける。『まひるのほし』(1998年)、『SELF AND OTHERS』(2000年)、『花子』(2001年)などのドキュメンタリー映画の他に、テレビ作品、展示映像、個人映画、編集・構成作品が多数ある。最新作は『阿賀の記憶』(2004年)。その後エドワード・サイードの遺志と記憶を追う『OUT OF PLACE』(仮題)を準備中。99年より映画美学校主任講師。2001年より京都造形芸術大学教授。2002年8月から文化庁派遣芸術家在外研究員としてロンドンに1年間滞在した
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。