出版社内容情報
現代日本の被災者はどのような権利を持っているのか!現代日本の被災者はどのような権利を持っているのか!
日本は自然災害大国だが、防災大国ではないはずだ!
大震災から、足かけ5年、未だ18 万人以上の被災者が仮設住宅で暮らし、生業の回復も充分ではない。
避難所収容は先進国の災害対策ではない!
長引く避難所・仮設収容は、心身の健康を害し、震災関連
自殺者数も154人に上る。
惨事便乗型(=創造的復興)の現状と問題点・人間的復興
を現場で対置した論攷
はじめに―綱島不二雄(元山形大学教授/農業経営論)
第1章 大震災からの復興―「創造的復興」と被災者の権利
―綱島不二雄
第2章 なぜ、日本の災害対応は発展途上国レベルに止まっているのか
―塩崎賢明(立命館大学教授/災害論)
第3章「 人間復興」と地域内経済循環の創出
―岡田知弘(京都大学大学院教授/地域経済学)
第4章 復興予算は復興のために使われているのか?
―宮入興一(愛知大学名誉教授/財政学)
第5章 自治体の災害対策が機能不全に陥るメカニズム
―川瀬憲子(静岡大学教授/地方財政学)
第6章 被災自治体の対応の実態と課題
―平岡和久(立命館大学教授/財政論)
第7章 大災害の際、人を救う金融・被害を増幅する金融
―鳥畑与一(静岡大学教授/金融論)
第8章 大津波と海洋資源、漁業、放射能汚染の状況と課題
―片山知史(東北大学教授/水産資源生態学)
第9章 復活する農漁村・停滞する地域●その理念と施策の相違
―綱島不二雄
第10章 いま、被害者は何求めているのか
―室崎益輝(関西学院大学教授/防災論)
まとめにかえて―岡田知弘
綱島不二雄[ツナシマフジオ]
元山形大学教授/農業経営論
岡田知弘[オカダトモヒロ]
京都大学大学院教授/地域経済論
塩崎賢明[シオザキヨシミツ]
立命館大学教授/災害論
宮入興一[ミヤイリコウイチ]
愛知大学名誉教授/財政論
内容説明
大災害の時代。「防災貧国」から「人間の復興」への転換を。本書の眼目は、憲法に基づく幸福追求権、生存権、そして財産権を保障する「人間の復興」への展望を示すことである。
目次
序章 大震災からの復興―「創造的復興」と被災者の権利
第1章 復興災害の構図と住まい・まちづくり
第2章 「人間の復興」と地域内経済循環の創出
第3章 大震災における復興行財政の検証と課題
第4章 大震災後の復興交付金事業と復興格差をめぐる諸問題―宮城県石巻市の事例を中心に
第5章 被災自治体の震災対応の実態と課題
第6章 東日本大震災における二重債務問題と人間復興における金融課題
第7章 大津波後の漁業、漁村と人口流出
第8章 農業・農村と漁業・漁村・漁港都市の復興の現状と課題
第9章 大震災後に作られた法律は、被災者を救済したのか
終章 大震災における減災思想とそのあり方
著者等紹介
綱島不二雄[ツナシマフジオ]
元山形大学農学部教授、農学博士(東北大学)。東北大学農学研究所講師、札幌大学経済学部教授を歴任。日本農業経済学会理事、日本フードシステム学会理事、家族複合経営論、フードリサイクルシステム論、化学肥料産業論、日本科学者会議地震・津波災害復興研究委員会委員長、東日本大震災復旧・復興支援みやぎ県民センター代表世話人
岡田知弘[オカダトモヒロ]
京都大学大学院経済学研究科教授、経済学博士(京都大学)。自治体問題研究所理事長、日本地域経済学会会長。地域開発政策論、地域経済論を専門に研究。1995年の阪神・淡路大震災以来、中越大震災、東日本大震災の被災地調査に取り組み、災害復興問題にも研究領域を広げている
塩崎賢明[シオザキヨシミツ]
立命館大学教授、神戸大学名誉教授。日本住宅会議理事長、兵庫県震災復興研究センター代表理事、阪神・淡路まちづくり支援機構代表委員。神戸大学助手、助教授、教授を経て現職。その間、オクスフォード大学(セントキャサリンズカレッジ)、バーミンガム大学で客員研究員。専門は住宅問題、住宅政策、都市計画。阪神・淡路大震災を契機に国内外の復興まちづくり、住宅復興研究に取り組む。住宅復興研究で2007年度日本建築学会賞(論文賞)受賞
宮入興一[ミヤイリコウイチ]
愛知大学名誉教授・客員所員、長崎大学名誉教授。経済学修士(大阪市立大学)。東京市政調査会藤田賞受賞(論文「災害対策と地方財政運営」、1995年)。財政学・地方財政学の見地から地域開発論に取り組んできたが、1982年の長崎大水害、1991年の雲仙普賢岳火山災害、とくに1995年の阪神・淡路大震災を契機に、災害の政治経済学の展開に本格的に取り組んでいる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
-

- 和書
- 百鬼園先生と私 中公文庫
-

- 電子書籍
- 宮本から君へ 12 SMART COM…
-
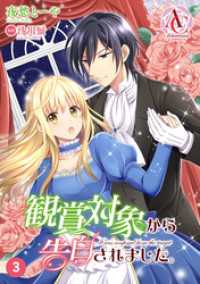
- 電子書籍
- 【分冊版】観賞対象から告白されました。…
-
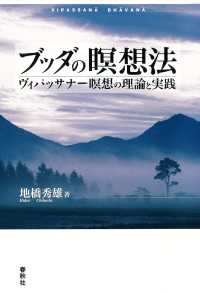
- 電子書籍
- ブッダの瞑想法 - ヴィパッサナー瞑想…
-

- 電子書籍
- 仮面ライダーアマゾン




