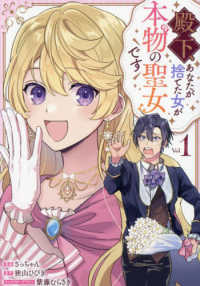内容説明
逸脱と不適応から帰結した罪を見つめようとする加害者たち、みずからの価値観を問い返しつつ彼らと対話する臨床家、仲間との対話・多職種との協働・スーパーヴィジョンを通じてポジションを相互検証する専門家集団―交差する3つの観点から加害者臨床の本質に迫る臨床試論。
目次
第1部 「あなた」=非行少年・受刑者という対象(社会を困らせる“魅力的な”人々;逸脱の理解―その核心と周辺;適応と不適応;事件と罪を見つめる;逸脱の起源;加害者臨床と「契約」)
第2部 「私」=心理臨床家という主体(私という主体‐実体性;援助者の「不実」;臨床家の利用可能性)
第3部 「わたしたち」という関係(仲間・異業種;トレーニングとしてのスーパーヴィジョン;薄氷の上のダンス;「別れ」について)
著者等紹介
門本泉[カドモトイズミ]
さいたま少年鑑別所統括専門官。早稲田大学大学院文学研究科(修士)、筑波大学大学院システム情報工学研究科(博士)修了。名古屋少年鑑別所、東京少年鑑別所、川越少年刑務所、府中刑務所等を経て、2019年4月より現職。臨床心理士、公認心理師、Teaching and Supervising Transactional Analyst(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Z
7
実践というほど実践ではないと思うが、優れた著作だと思う。犯罪に関わった者に対する臨床であり、①本人は臨床を望んているわけではのないこと②施設を出るまでという限定された期間を対象とするため、臨床の期間が精神医学や精神分析と異なり、十分とはいえない点に独自の点を感じたが、その中でもこの本に書かれる臨床に関する著者の基本態度は他の臨床形態でも通用するよう一般化されたものだと思う。「師匠は同じ分野の人間である必要はない」など、知に貪欲な人間しか出てこないだろう。2023/08/08
木麻黄
3
p208「以前担当した対象者が,再犯により再び自分の勤める職場に入ってくることがある。正直に告白すると,筆者は再犯を悲しく残念に思う一方で,彼らに再会できたことを単純に喜んでいる自分を見つける。これについて神田橋は,『共感の関係』だとかつてコメントした。」。この場面は,とある学会の質疑応答の際に,神田橋先生と筆者の質疑応答の中で交わされた場面ではないでしょうか。当時私はその場にいたのですが,その時のやり取りは今でも鮮明に覚えており,時に後輩らに語ることがあります。だから,すぐに分かったのである(ドヤッ)。2021/10/08
イカ
3
先日読んだ『刑務所しか居場所がない人たち』は、受刑者をとりまく環境(障害、生育環境など)に重点が置かれていた。何でも自己責任として引き受けるのではなく、他人や環境のせいにすることも必要な場合がある。受刑者の言い分に耳を傾け、受け入れ、肯定することも大切なことだ。 しかし、それが行き過ぎると、その人の主体性が軽んじられることにもなりかねない。その人は一方的に助けられる人、憐れむべき人ということになり、加害者であるという事実が薄められむしろ被害者のように扱われてしまうことさえある。2021/03/04
煮卵
1
最初の職場で出会った先輩の本。自分は今は別の世界にいるけど(門本さんも満を持して研究の世界に転じたようだ。)、司法関係者も必読だと思う。素敵な人が書いた真摯な本。とても専門的だけど、平易に書かれた本。
言いたい放題
0
半永久保存版2023/07/23
-
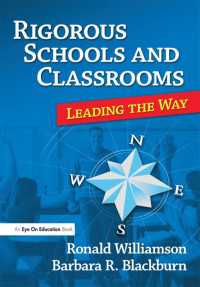
- 洋書電子書籍
- Rigorous Schools an…
-
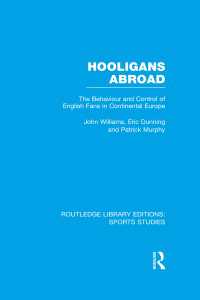
- 洋書電子書籍
- Hooligans Abroad (R…