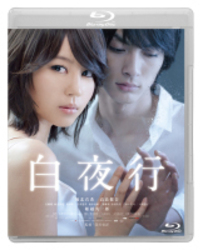出版社内容情報
認知症の予防とリハビリテーションを目指した「臨床美術」の活動について,その理論的背景と実際のプログラムの進め方を解説する。
1977年に彫刻家である金子健二は、子どもたちに真の芸術の楽しみ方を伝えるために子ども造形教室を設立し、独創的な美術教育活動を始めました。やがて地域の高齢者も参加するようになり、認知症予防、また認知リハビリテーションとしての「臨床美術」に結実していきます。
本書では、臨床美術の認知症に対するリハビリテーションの実践、認知症の病態メカニズムに臨床美術がどう関わるかという認知神経科学的考察を述べ、患者さんによる多数の作品の紹介と実際のアートプログラムの進め方とセッション構成を解説しています。
最終章では美術に関連した周辺領域の概念を援用した臨床美術の美学的な位置づけが考察され、科学と芸術双方の理論的なバックボーンを学ぶことができます。
カラー写真で掲載された患者さんの作品は、どれも個性豊かで生き生きとしており、一目で本書の魅力を感じることができるでしょう。
序文 宇野 正威
第1章 認知リハビリテーションとしての臨床美術
内容説明
臨床美術の認知症に対するリハビリテーションの実践、認知症の病態メカニズムに臨床美術がどう関わるかという認知神経科学的考察を述べ、患者さんによる多数の作品の紹介と実際のアートプログラムの進め方とセッション構成を解説。最終章では美術に関連した周辺領域の概念を援用した臨床美術の美学的な位置づけが考察され、科学と芸術双方の理論的なバックボーンを学ぶことができる。
目次
第1章 認知リハビリテーションとしての臨床美術(認知症が発症すると認知機能はどのように低下するか;認知症への働きかけと脳機能の活性化 ほか)
第2章 認知症の人たちの作品集―さまざまなアートプログラムから生まれた作品(なすを描く;アジの干物を描く ほか)
第3章 臨床美術のプログラムと臨床美術士の役割(臨床美術のアートプログラム;臨床美術のセッション構成―「音のアナログ画(カンボジア音楽)」実施を例に ほか)
第4章 臨床美術へのオマージュ―美学の視点から(臨床、「現場に立つこと」;「生きる喜び」を共有すること ほか)
おわりに―芸術は「言葉」を超えることができるコミュニケーション
感想・レビュー
-

- 電子書籍
- 【分冊版】いちこえ、にふり、タチアオイ…