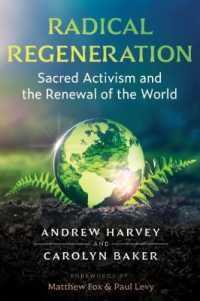出版社内容情報
素行障害は,多くの精神疾患と異なり,社会的な規範に対する問題行動によってのみ規定される。その困難な対応への確かな指針を示す。
素行障害(conduct disorder:CD)は,社会的な規範に対する反復的かつ複数の分野にわたる問題行動によって規定される疾患概念である。それは,被虐待児に発現の親和性が高く,発達障害の子どもにも同じ傾向があるとされる。また,CDの存在によって,併存する精神疾患の治療は難しくなり,対応困難例とされることも多い。
診断・評価にあたっては,DSMやICDに基づく診断が半構造化された基準にしたがって行われるべきであり,それに加え本書では,下位分類を評価するCDCL(conduct disorder check list)の有効性を示す。治療については,まず性非行に対する自立支援施設での治療教育プログラムの成果を明らかにする。
さらに,CDに対する治療・援助は一機関のみでは難しい。そこで地域専門機関の連携システムの設置と,それを通じた複数機関による介入を紹介する。そして,地域専門機関への調査から,その連携システムには,医療的な評価や高度の治療が求められることも明らかにされた。
本書では,これらの研究成果を導入した,素行障害に対する診断と治療のガイドラインを示す。
はじめに(齊藤万比古)
1章 素行障害の概念
1.非行概念の有効性と限界(橋本牧子)
2.疾患概念としての「素行障害」成立史(安藤久美子)
3.各種臨床における素行障害の枠組み
a)保健・医療における素行障害の枠組み(来住由樹・中島豊爾)
b)児童福祉における素行障害の枠組み(近藤直司)
c)少年司法における素行障害の枠組み(奥村雄介)
2章 素行障害の評価・診断
1.素行障害の評価・診断(宇佐美政英・齊藤万比古)
2.素行障害の医学的診断基準と評価尺度
a)医学的診断基準(ICD-10とDSM-?W-TR)(安藤久美子)
b)評価尺度および心理検査
?@子どもの行動チェックリスト(Child Behavior Check List : CBCL)(清田晃生)
?A素行障害チェックリスト(Conduct Disorder Check List : CDCL)(奥村雄介・元永拓郎)
?B反抗挑戦性評価尺度(Oppositional Defiant Behavior Inventory : ODBI)(原田 謙)
?C知能検査(田崎美佐子)
?D人格検査(今村洋子・寺村堅志)
c)医学的・神経学的検査(酒井文子)
3.素行障害の併存障害
a)発達障害(原田 謙)
b)脳器質性疾患(てんかんなど)(市川宏伸)
c)情緒障害(不安障害、気分障害など)(市川宏伸)
d)人格障害と精神病性疾患(来住由樹・中島豊爾)
e)物質乱用(松本俊彦)
4.注目すべき要因
a)社会的環境(冨田 拓)
b)虐待および不適切な養育環境(犬塚峰子)
c)不登校・ひきこもり(境 泉洋・近藤直司)
3章 素行障害の治療
1.素行障害の治療(宇佐美政英・齊藤万比古)
2.医療機関による介入
a)外来治療(来住由樹・中島豊爾)
b)入院治療(成重竜一郎)
3.児童相談所による介入(影山 孝)
4.地域保健機関による訪問支援(ひきこもり支援を中心に)(新村順子・田上美千佳・近藤直司)
5.地域連携
a)市川地区および大分地区における取り組み(宇佐美政英)
b)岡山地区における取り組み(伏見真里子・来住由樹)
6.児童自立支援施設による介入(冨田 拓)
7.少年院による介入
a)一般少年院での介入(性非行に対する治療を中心に)(藤岡淳子)
b)医療少年院での介入(奥村雄介)
8.モデル的取り組み
a)マルチシステミックセラピー:Multisystemic therapy(MST)(吉川和男)
b)施設内における性非行少年への治療教育(藤岡淳子)
4章 事例
1.背景に虐待を認める小児期発症型素行障害の事例(箕和路子)
2.広汎性発達障害を併存障害にもつ素行障害事例の入院治療(成重竜一郎)
3.注意欠陥/多動性障害を併存障害にもつ素行障害事例の外来治療(原田 謙)
4.入院治療を必要としたDBDマーチを認めた注意欠陥/多動性障害事例(渡部京太)
5.長期のひきこもりと家庭内暴力を認めた事例(近藤直司)
6.児童自立支援施設から地域への復帰が困難であった事例(冨田 拓)
7.性的非行を認めた素行障害女児への介入(浅野恭子)
8.警察および司法機関との連携に工夫を要した事例(来住由樹・中島豊爾)
5章 今後の展望と課題
1.今後の課題(齊藤万比古)
【著者紹介】
編者略歴
国立国際医療研究センター 国府台病院 精神科部門診療部長
内容説明
繰り返し起こる子どもの反社会的行動を「素行障害」という医療的視点から支援する。
目次
第1部 素行障害の概念(非行概念の有効性と限界;疾患概念としての「素行障害」成立史 ほか)
第2部 素行障害の評価・診断(素行障害の評価・診断;素行障害の医学的診断基準と評価尺度 ほか)
第3部 素行障害の治療(素行障害の治療;医療機関による介入 ほか)
第4部 事例(背景に虐待を認める小児期発症型素行障害の事例;広汎性発達障害を併存障害にもつ素行障害事例の入院治療 ほか)
第5部 今後の課題
著者等紹介
齊藤万比古[サイトウカズヒコ]
1948年長野県生まれ。1975年千葉大学医学部卒業。同年同仁会木更津病院精神科勤務。1979年国立国府台病院精神科勤務、児童精神科の専任となる。1999年国立精神・神経センター国府台病院心理・指導部長。2003年国立精神・神経センター精神保健研究所児童・思春期精神保健部長。2006年国立精神・神経センター国府台病院リハビリテーション部長。2008年国立国際医療センター国府台病院第二病棟部長。2010年国立国際医療研究センター国府台病院精神科部門診療部長。2013年より恩賜財団母子愛育会総合母子健康センター愛育病院小児精神保健科部長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。