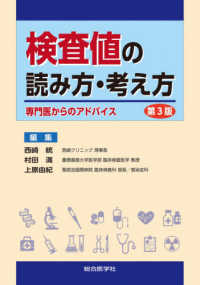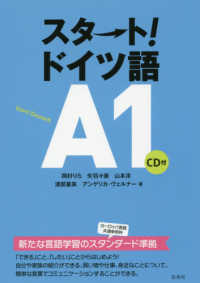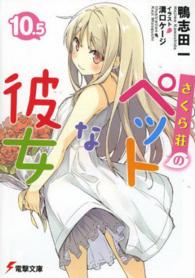目次
臨床心理アセスメントとは何だろうか
問題意識
医学的診断を超えて
問題のメカニズムを探る
アセスメントを意味あるものにする
介入の方針を定める
初回面接
改めて臨床心理アセスメントを考える
著者等紹介
下山晴彦[シモヤマハルヒコ]
1983年、東京大学大学院教育学研究科博士課程中退。東京大学学生相談所助手、東京工業大学保健管理センター講師、東京大学大学院教育学研究科助教授を経て、東京大学大学院・臨床心理学コース教授。博士(教育学)、臨床心理士(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。