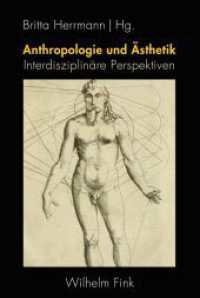出版社内容情報
《内容》 本書では,MRI(Mental Research Institute)や解決志向(solution-focused)によるアプローチをはじめ,短期力動的セラピー,対人関係的セラピー,認知行動療法,システム的/戦略的セラピー,等,現在の問題を査定しその問題の除去に力点をおくという‘ブリーフサイコセラピー’の基本的な考え方と実践で役立つ多くのヒントを紹介する。
心理療法の実践はそれを行うものの価値観や信念といやがうえにも密接に結びついている。著者の立場は,「治療の目標や焦点を明確にする」という理念に貫かれ,特定の理論だけに盲従することを目的とはしていない。したがって,本書で述べられる実際的な知見は,効果的な心理療法一般に通じる総合的な考え方ともいえ,臨床家が単一アプローチのみを適用しようとする悪循環に注意を促している。近年,急速に浸透しつつある「ブリーフ・セラピー」の基本原則を身につけるための実践的な入門書である。
《目次》
□主な目次
ブリーフ・セラピーの原則●目次
第一章 本書の利用法
ブリーフ・セラピー知識クイズ
クイズの答え
第二章 ブリーフ・セラピーとは何か?
キーとなる特徴のまとめ
アプローチによるブリーフ・セラピーの相違
短期精神力動的アプローチ
認知・行動的アプローチと戦略的アプローチ
ブリーフ・セラピーの志向する価値
第三章 なぜブリーフ・セラピーを実践するのか?
なぜブリーフ・セラピーの実践をしないか?
第四章 ブリーフ・セラピーの手続き概要 :治療のプロセス
手続き概要の要約
1 インテークの前の仕事
2 初回セッションの課題
3 第二回目以降のセッションにおける課題
4 成果の維持
5 治療の終了
6 結果の記録
第五章 治療の進行に妨げとなるものを克服する:ヒントと技法
クライエント自身が治療に対して非協力的なときの戦略
第六章 臨床現場における特別な話題
ブリーフ・セラピーの禁忌
家族やカップルや子どもとの作業
ブリーフ・セラピーによる集団療法
短期治療で正式な査定を活用すること
多文化主義とブリーフ・セラピー
薬物療法とブリーフ・セラピー
薬物療法を要請するためのガイドライン
ブリーフ・セラピストになること
ブリーフ・セラピーを理解するための用語集
内容説明
本書では、MRI(Mental Research Institute)や解決志向(solution‐focused)によるアプローチをはじめ、短期力動的セラピー、対人関係的セラピー、認知行動療法、システム的/戦略的セラピー等、現在の問題を査定しその問題の除去に力点をおくという‘ブリーフサイコセラピー’の基本的な考え方と実践で役立つ多くのヒントを紹介する。近年、急速に浸透しつつある「ブリーフ・セラピー」の基本原則を身につけるための実践的な入門書。
目次
第1章 本書の利用法
第2章 ブリーフ・セラピーとは何か?
第3章 なぜブリーフ・セラピーを実践するのか?
第4章 ブリーフ・セラピーの手続き概要:治療のプロセス
第5章 治療の進行に妨げとなるものを克服する:ヒントと技法
第6章 臨床現場における特別な話題
著者等紹介
岡本吉生[オカモトヨシオ]
1979年京都府立大学文学部卒業。1980年家裁調査官補(大阪家裁堺支部)。1983‐1997年家裁調査官。1993年Mental Research Institute留学。1997年筑波大学大学院修士課程修了。現在、埼玉県立大学保健医療福祉学部助教授。日本犯罪心理学会理事、国際カウンセリング協会理事
藤生英行[フジウヒデユキ]
1983年埼玉大学教育学部卒業。1985年東京学芸大学大学院修士課程教育学研究科学校教育専攻臨床心理学講座修了。1992年筑波大学大学院博士課程心理学研究科心理学専攻修了。博士(心理学)。1992年筑波大学技官、1993年同大助手、1995年同大学校教育部講師、1997年同大助教授を経て、現在、上越教育大学学校教育学部助教授。児童・生徒のメンタルヘルスに関する研究、発達臨床心理学に関する研究に従事。日本心理学会、日本教育心理学会、日本発達心理学会、日本カウンセリング学会、日本心理臨床学会、日本母性衛生学会、American Psychological Association会員
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。