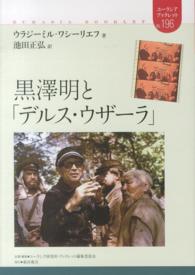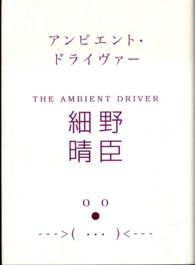出版社内容情報
地域政策研究をチームとして進めるためには、取得した地理空間データをいかに管理し共有するかが課題となる。政策立案に携わる実務者、政策研究を志している研究者や学生、GIS を活用したまちづくりを実践している方々を対象に、「地理空間データの取得・開発」と様々なツールを用いた「情報共有のためのWebGISアプリの構築」の手法について詳しく解説する。
目次
第1章 地域研究のための「道具」
第2章 情報統合管理システムの環境整備
第3章 Djangoを用いたWebアプリケーション開発の基本
第4章 PostgreSQLデータベースを用いたWebアプリケーションの開発
第5章 オープンデータの二次加工
第6章 多様な情報源による地理空間データの作成
第7章 スパース道路ネットワークにおけるトポロジーデータセットの作成
第8章 GeoDjangoを用いたWebGISアプリケーションの作成
著者等紹介
蒋湧[ショウユウ]
1955年生まれ、筑波大学大学院社会工学研究科経営工学専攻修了。東京都立大学経済学部助教を経て、愛知大学地域政策学部、愛知大学大学院経営学研究科教授。博士(経営工学)。応用数学、データ工学と地理空間情報科学などを専門とする(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
39
いきなり、東栄町の地図が出てきたので、非常に懐かしく思い出した。また、訪れてみたくなった。光ファイバー幹線コスト階級と年齢別人口分布の関係が図6-46に出てくるようだ(口絵カラー写真)。100頁から詳説がある。数式としては、Cost=∑n(n番配線の長さ/n番配線を共有する世帯数)で、nは中継基地局からn番目の接続配線。私が院生だった20数年前と比べれば、GISやRSはかなり進歩したと思える。副題にあるソフトもそのうち使いたいが、専門分野だけでは生きていかれないと思う。分析ツールぐらいは知っておきたい。2024/12/27