- ホーム
- > 和書
- > 人文
- > 図書館・博物館
- > 図書館・博物館学その他
内容説明
本書は、ギリシア語とラテン語の文献が保存されてきた過程の全体像を大まかに描こうと努め、写本が使われていた時代にテクストはどのような危険にさらされていたかを述べ、また古代や中世の読者や学者たちは古典テクストを保存したり伝承したりすることにどれだけ関心を寄せていたかを記した。
目次
第1章 古代
第2章 東のギリシア語圏
第3章 西のラテン語圏
第4章 ルネサンス
第5章 ルネサンス以降
第6章 テクスト批判
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
サアベドラ
19
古代ギリシアやローマの作家によって書かれたテクストがどのような過程を経て現代に伝えられたか、すなわちどのような人々によって筆写され、注を付けられ、再発見され、校訂され、出版されてきたかという、広い意味での文献学の歴史の概説書。西洋古典を勉強している人はもちろん、古代から近世にいたるまでのインテレクチュアル・ヒストリーに関心のある人でも興味深く読めると思う。扱っているトピックが広すぎて一つ一つの記述が短い分、文献案内が充実している。教科書みたいな本で、実際、欧米では大学の教科書として使われているという。2014/12/03
Z
9
いい本だった。ギリシアローマの文献が如何に現代に伝えられたかをたどりつつ文献を巡る知の有り様までを考察する人文学史。図書館そして遅れて教会というのが古代の知の拠点であり、古代の文献収集から文献学が発達。ルネサンス期には個人の蔵書も発達し、教会間の人の移動や、布教活動にともない本が移動し知のネットワークが形成されていく過程は面白かった。俗語革命以前の知の有り様、いわゆる古典的ヨーロッパの知がたどれためになる2016/03/30
-

- 電子書籍
- GOLF TODAY 2022年4月号
-
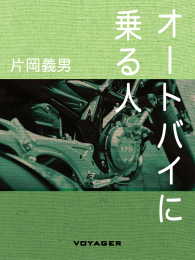
- 電子書籍
- オートバイに乗る人
-
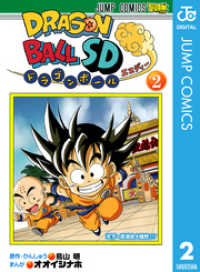
- 電子書籍
- ドラゴンボールSD 2 ジャンプコミッ…
-
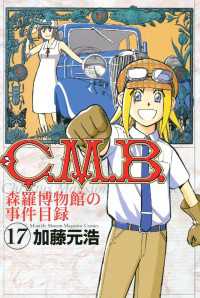
- 電子書籍
- C.M.B.森羅博物館の事件目録(17)
-
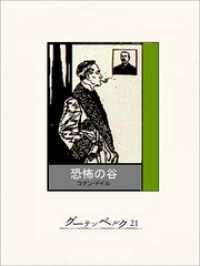
- 電子書籍
- 恐怖の谷




