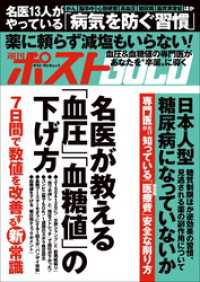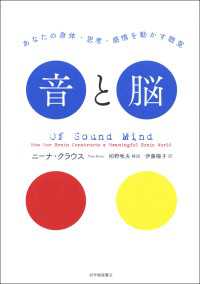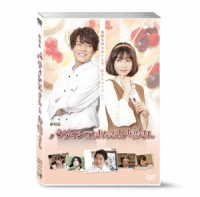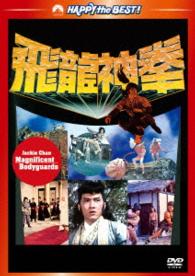出版社内容情報
増大した資本がグローバルに動き回ることによる資産価格や為替相場の急激な変動。さらに新興国の台頭、地域紛争などにより国際通貨制度はつねに揺れ動いている。
本書は、歴史的・段階的に国際通貨制度の成り立ちを考察することによって、その課題とあるべき姿を模索する。
【目次】
序 章「ドル本位制」のゆくえ
第1章 国際収支とは
第1節 国際収支表
第2節 国際収支の黒字・赤字とは――国際収支のとらえ方と種類
第3節 国際投資ポジション
補論1 マネタリー・ベースとマネー・ストック
補論2 新たな国際収支標準項目
補論3 デリバティブ取引の成長
第2章 世界貨幣と外国為替制度
第1節 貨幣の生成と世界貨幣
第2節 外国為替制度
第3章 国際通貨と国際決済
第1節 国際通貨と国際通貨制度史
第2節 外国為替相場
第3節 外国為替相場と国際決済
補論1 直物為替相場と先渡為替相場
補論2 購買力平価説
第4章 国際金本位制の構造
第1節 国際金本位制とは
第2節 ポンドの国際通貨化の条件
第3節 国際金本位制の機能
第4節 国際収支の調整を巡る諸説
補論1 イングランド銀行
補論2 ロンドンの銀行
第5章 ブレトン・ウッズ体制と変動相場制への移行
第1節 ブレトン・ウッズ体制の成立と展開
第2節 ブレトン・ウッズ体制の崩壊と変動相場制への移行
第3節 変動相場制の現実と課題
補論1 「流動性のディレンマ論」を巡る論争
補論2 不換の国際通貨ドルを巡る論争
第6章 プラザ合意以降の「ドル本位制」
第1節 1985年プラザ合意と「ドル体制」の変容
第2節 1990年代のアメリカ経済の復活とグローバリゼーションの深化
第3節 国際通貨ドルの地位(138)
補論1 CDS(Credit Default Swap)
補論2 空売り(short selling)
第7章 アメリカ金融危機と危機対策
第1節 アメリカ発世界金融危機
第2節 アメリカ金融危機における財政・金融政策の展開
第3節 財政・金融政策の帰結
補論1 中央銀行の買いオペと政府からの直接国債買い入れ
補論2 影の銀行(シャドーバンク)
第8章 世界金融危機後の「ドル本位制」
第1節 アメリカの国際資本取引のフローとストック分析
第2節 アメリカ経常収支赤字ファイナンスを巡る論争
補論1 ISバランス・アプローチ論
第9章 「ドル本位制」の将来
第1節 国際通貨ドルの流通根拠を巡る議論
第2節 アメリカの金融政策の正常化と中国人民元の国際化
第3節 「ドル本位制」の新段階――コロナショックとウクライナ危機
内容説明
国際通貨制度の歴史から「ドル本位制」の行方まで。「ドル本位制」はどこに向かうのか?国際通貨制度を歴史的・段階的に考察し、新興国の台頭、コロナショック、地域紛争など不安定化する国際情勢の中で、国際通貨制度のあるべき姿を考える。
目次
序章 「ドル本位制」のゆくえ
第1章 国際収支とは
第2章 世界貨幣と外国為替制度
第3章 国際通貨と国際決済
第4章 国際金本位制の構造
第5章 ブレトン・ウッズ体制と変動相場制への移行
第6章 プラザ合意以降の「ドル本位制」
第7章 アメリカ金融危機と危機対策
第8章 世界金融危機後の「ドル本位制」
第9章 「ドル本位制」の将来
著者等紹介
松浦一悦[マツウラカズヨシ]
現在、松山大学経済学部教授、博士(国際関係学)。1963年熊本県生まれ。大分大学経済学部卒業。同大学在籍中、1984年に米国サンフランシスコ州立大学へ文部省国費派遣留学。1991年3月、同志社大学大学院商学研究科博士課程単位取得退学。1991年4月より松山大学経済学部専任講師。同大学助教授、英国ケンブリッジ大学政治経済学部客員研究員を経て、2000年4月より現職。日本EU学会理事(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。