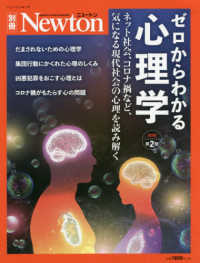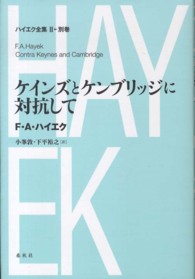内容説明
総歩行距離2000キロ以上にもおよぶ、老若男女が毎日歩き続ける伊勢神宮への旅は、どのようにして可能となったのでしょうか。旅のルートと歩行距離を割り出し、徒歩での旅を可能とした旅人の身体技法や装い、健脚を支えた街道の交通インフラやマナー、旅の家計簿などから、江戸の庶民に愛された「お伊勢参り」の旅をひも解きます。
目次
第1章 旅のルートと歩行距離
第2章 幕末~明治初期の日本人の歩き方
第3章 街道の必須アイテム「棒」―使い道と身体技法
第4章 旅の履物
第5章 旅の家計簿
第6章 旅人の健脚を支えたもの
第7章 近代化による旅の変化
著者等紹介
谷釜尋徳[タニガマヒロノリ]
東洋大学法学部教授。日本体育大学大学院博士後期課程修了。博士(体育科学)。専門はスポーツ史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
えんちゃん
65
健脚最高。幕末から明治初期までの近世後期の長距離徒歩旅行のアレコレ。莫大な資料に基づく旅のデータと考証。ルート・距離・歩き方・必須アイテム・費用・マナー・道中のお楽しみ等等。とても面白かった。近所に今も残る東海道の松並木。江戸の旅人に思いを馳せて、今度じっくり見てみよう。2021/09/01
きみたけ
54
著者は東洋大学法学部教授で体育科学博士の谷釜尋徳氏。江戸時代の「お伊勢参り」は長距離徒歩旅行。旅行紀に書かれた旅のルートと歩行距離から徒歩での旅を可能とした旅人の身体技法や装い、健脚を支えた街道の交通インフラやマナーを詳細に解説しています。 電車や飛行機のなかった時代「旅行=歩く」が当たり前であり、2,000キロもの距離を歩行するのはまさにアスリート並み。農作業で鍛えられた足腰がものを言うのでしょうね。60日にもおよぶ徒歩旅行は現代ならば世界一周旅行の感覚だと思います。あ~、旅行に行きたい~😣2021/12/11
ミーママ
40
図書館の本📚️ 江戸時代の旅人の様子がしりたくて読んでみた! 本当に健脚だと改めて思った。今度は女子旅を読んでみたい❗2023-1322023/10/18
かずぼう
28
江戸時代の旅人の歩行距離に驚愕、1日平均35km、総距離2000kmにもおよぶ。この頃は、メタボとは無縁なんだろうな。 興味深かったのは、『講』というシステム、旅行したい賛同者を募って集金、お金が貯まったら順番に旅行を楽しむ。おもしろい。2021/08/26
テツ
27
江戸時代の庶民によるお伊勢参りについての諸々。毎日毎日30km以上歩いての巡礼の旅と聞けば揺るぎない鉄のような信仰心に裏打ちされていると想像してしまうけれど、この時代にはお伊勢参りは娯楽だった。一生に一度あるかないかの長旅。生まれ馴染んだ土地を離れて遥か彼方を目指し自身の脚だけを頼りに歩いて行く途中に目にするのは見たこともない世界。SNSなど夢にも思わない時代に噂に聞いただけの名所を実際に目にしたときの感動は凄まじいだろうな。現代ではこんなに歩くことはないけれど読んでいるうちに旅をしたくなりました。2020/09/02
-

- DVD
- 偽りのオペレッタ