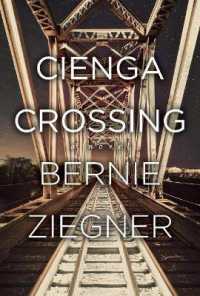内容説明
就職活動や労働の場において、当事者が直面する様々な困難を明らかにし、その法的解決方法を分析。また、ILO(国際労働機関)や先進的な企業の取り組み、当事者にむけた就職支援の紹介を通じて、誰もが自分らしく働ける職場とはどのようなものか考えます。巻末には、これだけはおさえておきたい用語解説・判例・法令も収録。
目次
序論 LGBTIの包括的権利保障をめざして
第1章 LGBTの人権保障と労働法
第2章 LGBTが働きやすい職場づくりへ向けた企業の取り組み
第3章 LGBTIの雇用と労働に関する国際労働機関(ILO)の政策
第4章 LGBTが職場で直面している困難の法的解決に向けて
第5章 LGBTの就職と就労
用語解説・判例・法令
著者等紹介
三成美保[ミツナリミホ]
1956年生まれ。奈良女子大学副学長、同大学研究院生活環境科学系教授。専門:ジェンダー法学、ジェンダー史、西洋法制度。著書多数(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
katoyann
28
セクシュアル・マイノリティの雇用に関する諸課題について論じられている研究書。職場では、性的指向・性自認に関する偏見や差別が横行しやすく、具体的には当事者がセクシュアル・ハラスメントの被害に遭いやすい。また、トランスジェンダーは年収200万円未満が27.5%に達するという。これは、そもそも就職採用の段階で落とされるケースがあること、また服装規定等が当事者のジェンダー・アイデンティティに合わなかったり、トイレの利用制限があったりして、職場で精神的苦痛を経験する機会が多いからだという。権利保障の課題が分かる。2022/11/22
makoto018
6
子育て、介護、非正規雇用、障がい者など、個々の状況に理解し、働きかたの多様性(ダイバシティ)により、人材確保と組織全体の生産性アップというのが近年の風潮。その先にあるのが、このLGBTIの尊重。法整備やハード面での対応は比較的容易かもしれないが、意識の問題がいちばん難しい。男女共生・女性活躍が、20年以上かかってようやく少しずつ意識変容に繋がってきている 現状を考えるとなかなか。まずは、子どものうち、若いうちからですよね。その意識がネイティブな世代が増えれば、組織も上の世代の意識も変わるだろうから。 2021/01/03
カモメ
3
LGBTIに関係する雇用や法律について知ることができた。現在、性的マイノリティに関する労働法上の法規制はなく均等法もLGBTへの適用は想定されていないが、セクハラは同性に対するものも含まれる。また、ハラスメントの範囲にはジェンダーハラスメントも含まれている。筆者はLGBTIに関する新たな立法が必要と主張し、具体的にはトランスジェンダーに関して障害者雇用促進法に規定される合理的配慮と同様の規定追加、要配慮個人情報に性的指向と性自認の文言追加、社会保障等において同性パートナーを配偶者と同等に扱う等である。2021/11/24
つーちゃん
1
LGBTの雇用に焦点が当てられている。 章によって著者が違う。それぞれ専門家(弁護士、団体職員など)が担当。 どの著者も感情がないので、フラットに、今起こっていること、今取り組まれていること、今後どうあるべきかが分かる。 報告書のような感じ? 冒頭、コンパクトに日本のLGBT歴史がまとまっているのもgood.2021/06/26