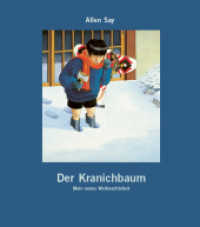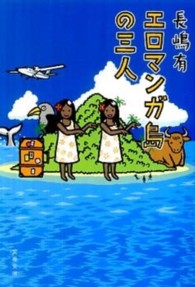内容説明
離れる他に、できることはないのだろうか。病理/非病理、偽物の愛/真実の愛、不幸/幸福、支配・従属/支え合いなど、多くの両義性を抱える「共依存」をめぐる言説を分析。そこに存在する倫理観を暴き出すことで、臨床の専門家や各領域の理論家が見逃してきた倫理と現実を提示する。
目次
共依存という生き方
第1部 共依存の概念史(共依存概念の誕生史;共依存の病理化;共依存と精神分析)
第2部 共依存の理論とその倫理観(共依存とフェミニズム;共依存とトラウマ論;共依存の回復論)
「異常者」という「忘れられた存在」
著者等紹介
小西真理子[コニシマリコ]
1984年岡山県岡山市生まれ。2014年立命館大学大学院先端総合学術研究科一貫制博士課程修了。2014年博士(学術)立命館大学。現在、日本学術振興会特別研究員PD(国際基督教大学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
キク
53
共依存という概念は学会で定義されたのではなく、アルコール依存者へのケアワーカーたちが臨床的に気付いたのが始まりだった。アルコール依存者の横で献身的に寄り添っている妻は、無意識に夫の回復を妨害していることが多い。アルコール依存者の回復のためには、まず献身的な態度で「受難者」かつ「支配者」であろうとする妻を引き離すことが重要だと、現場のケアワーカーが発見する。依存者と、依存者に必要とされることを渇望する者は、合わせ鏡のように依存関係を反射して深めていく。泣きたくなるけど現場で発見された事実だ。向き合うしかない2025/01/12
香菜子(かなこ・Kanako)
27
共依存の論理―必要とされることを渇望する人びと―。人から必要とされること自体は素敵なことだけれど、それだけが目的化してしまって見捨てられ不安から自分の意志や希望よりも他者の意志や希望を優先してしまっている人は共依存の危険信号。共依存問題が難しいのは、共依存の当事者たちが共依存状態にあることを自覚できないからだと思う。2018/10/09
ゆう。
23
共依存とは何か、それはとても難しい。人間関係の歪みではあるが、自分という人格が歪んだ依存関係ともいえる。人間は依存しあわなければ生きていくことはできない。しかし、それが病理化したときに、支配関係がうまれ、それは他人だけではなく自分をも支配し、苦しむのだろう。この本は著者の博士論文でもあり、学問的にも精密であった。2020/03/06
富士獣
8
共依存の定義や歴史からアダルトチルドレンのトラウマ論や共依存回復論まで詳細に検討した信用度の極めて高い本。著者の博士論文を元にしているだけあり、極めて丁寧で論理的な構成と文章になっている。精神分析理論や、フェミニズムによる共依存概念批判に対する、検討も興味深い。共依存言説を鳥瞰した上でそこに内在する倫理の考察が本著の真骨頂。 軽く概観を掴みたい場合や共依存者が自助本として使う場合の適切さは不明だが、門外漢がしっかり1冊学ぶという目的では、日本語による博論レベルの精度の共依存概論として、非常に勉強になった。2019/05/26
ひつまぶし
4
論文調の文体のわりに読みやすい。共依存概念自体が前提とする倫理の抑圧性を告発し、オルタナティブな生のあり方を模索することを課題としているのだろう。しかし、もう一歩踏み込めていない。治療を前提とするがゆえに共依存概念は社会批判的視点が弱い。それは精神医療や心理療法の限界でもあるだろう。しかし、そこを批判するだけなら、さほど難しい話にはならない。概念成立の社会的、理論的な整理を行った前半は勉強になった。後半は、分析の視点がはっきりしないため、著者の主張を補強するために事例が恣意的に並べられている印象を受けた。2024/03/27