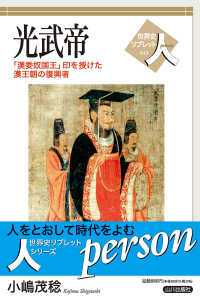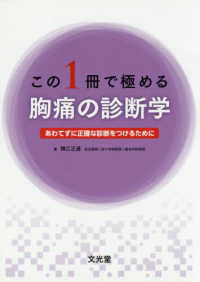目次
第1章 デカルトからスピノザへ(物体(延長)の世界
感覚について―『情念論』から
デカルト以後のオランダの思想状況)
第2章 スピノザにおける命題―限定は否定である(絶対的概念と相対的概念;主体なき概念;ヘーゲル的否定)
第3章 スピノザの『神学=政治論』における社会と国家(ホッブズとスピノザの共同社会形成論;スピノザの自生的社会形成論)
第4章 思考の自由と現実の自由―デカルトにとっての自由(デカルトの運動論;アリストテレスと古代マヤの運動論;デカルトに対する反論;スピノザによるデカルト二元論の克服)
第5章 ランゲの社会形成論―『市民法理論』を読む(希代のジャーナリスト・弁護士;法律の起源と現状;社会形成の秘密;所有精神の浸透;奴隷制と社会;現代の奴隷制;自由の幻想)
著者等紹介
大津眞作[オオツシンサク]
1945年大阪府に生まれる。1972年東京都立大学人文科学大学院仏文学修士課程修了。1980年甲南大学文学部助教授。現在、甲南大学文学部教授。専門はヨーロッパ社会思想史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
うえ
7
「19世紀末…リシュタンベルジュが、その幅広い18世紀社会主義研究でランゲの思想史的位置づけを明確にした。彼は…その「現状批判」の「激しさ、力強さは、抽象的な構築の試みやユートピアのプランや道徳学説などよりも、既成の秩序にとってはるかに危険なものである。所有権と社会をめぐる古い理論をゆるがすために、彼は彼なりに強力な貢献をした」と評価している。そして…マルクスがランゲの『市民法理論』を高く評価し…「資本論」第一巻では、ランゲの「法の精神は所有である」という表現を法律学的幻想に対する批判的警句として用いた」2020/04/16
-

- 和書
- 兵庫県南部地震と地形災害