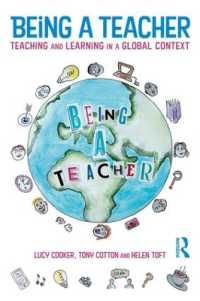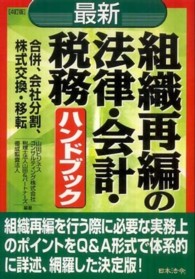出版社内容情報
1巻のところにも書きましたが、絵本を読んであげるだけじゃなく、散歩のとき蝶々が飛んでいたら「ちょうちょう」のサインを、食器や洋服にイヌやウサギが描かれていたら「いぬ」「うさぎ」のサインを、赤ちゃんに実際にして見せてあげてください。
いろいろな場面で、いろいろなときにサインをしてあげることで、赤ちゃんは物には名前があること、お母さんの手の動きに特別な意味があること、それが動物や物を表していること、などに気づいていくのです。
絵本に出てくる動物の写真などがあれば、それをトイレや冷蔵庫、赤ちゃんのベッドなどに貼り、機会があるごとに、その写真を指さしながらサインをして見せてあげるものよい方法です。テレビにその動物が出てきたときも、その動物のサインをして見せてあげるよいチャンス。そうやって、普段の生活のなかにベビーサインをどんどん取り込んでいってください。そうすれば、赤ちゃんがベビーサインを見る機会が増えますから、赤ちゃんはそれだけ早くベビーサインに慣れることができます。
また、ベビーサインを教えるときは、赤ちゃんの手をとって実際に動かしてあげましょう。バイバイを教えるとき、赤ちゃんの手をとって「バイバイ」と動かってみてください。ベビーサインに決まった形はありません。赤ちゃんがやりやすい、かんたんなサインを好きなように作っていいのです。
日常生活のなかで「シー」っと言って唇に指をあてたり、眠いときにネンネと言って手を頬にあてたりしますよね? 実は、あれも立派なサインなのです。だから、サインをむずかしいものだと考えないで、自由に楽しく、サインを作ってみてください。
自分でサインを作ることがむずかしいようなら、『ベビーサイン』のなかにもっとたくさんサインが載っていますので、そちらを参考にしてください。
〈『もぐもぐおいしいね』の紹介(3)のところにも、ベビーサインの教え方のコツが書いてあります〉
ベビーサインをしている赤ちゃんを初めて見たときは、本当に驚いた。「あなた、ほんとうに赤ちゃんなの?」と言いたくなるほど、しっかりした顔をしていたからだ。
お母さんに、いつでも自分の意志をはっきり伝えることができるという自信と安心があるからだろうか。とにかく赤ちゃんが落ち着いていて、いかにも利発な顔をしているのだ。
ある日のこと、ベビーサインをする赤ちゃんのそばで、その赤ちゃんのお母さんを交えて大人同士の会議をしていた。普通だったら、赤ちゃんが退屈してぐずりだす場面。その赤ちゃんも退屈したのか、一人で部屋のなかをぐるぐると歩きまわっていた。
と、突然、赤ちゃんが壁を指さして「さかな」のサイン。お母さんはすぐに、赤ちゃんが壁にかかっている魚の絵のことを言っているんだとわかって「うん、うん、さかなだね」と、こちらもサインとジェスチャーだけで赤ちゃんにお返事。
普通だったら言葉にならない奇声を発してお母さんの注意を引き、大人の邪魔をしてしまうはずなのに、赤ちゃんは自分の発見をお母さんに知らせただけで大満足。そのあとも、いろいろなものを見つけては、お母さんとサインを使った会話を続けていた。
会議のあとは、みんろう。すごいよ、赤ちゃんて!
育児をしていると、疲れ果てて「もういや! 子どもなんて産むんじゃなかった」と叫んでしまいそうになることが何度もある。育児の大変さを理解してくれる人が身近にいれば少しは癒されるが、残念ながら育児の大変さはなかなか理解してもらえない。理解されないからよけいに、母親にとって育児はつらいものになってしまう。育児のつらさは、孤独感にあると言ってもいいだろう。
だからこそ、赤ちゃんと「心を通わせること」が必要だと思う。
あなたの赤ちゃんは、あなたのことが大好きだ。どんなに失敗ばかりの親であっても、どんなに未熟な人間であっても、赤ちゃんはいつもあなたを受け入れ、許してくれる。……考えてみれば、それってすごいことだよね!?
(3)に続く。