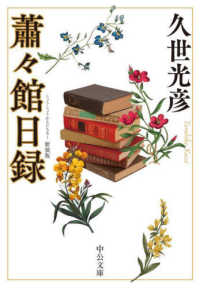目次
第1章 神話から宇宙の仲間へ
第2章 木星・土星の見方、楽しみ方
第3章 木星・土星の素顔
第4章 木星と土星の衛星
第5章 探査機の歴史と成果
第6章 巨大ガス惑星の形成をたどる
著者等紹介
鳫宏道[ガンヒロミチ]
1953年生。東京理科大学理学部卒業。1976年から天文担当学芸員として平塚市博物館に勤務。平塚市博物館館長、日本プラネタリウム協議会理事長、国際科学映像祭実行委員長を歴任。現在、JAXA宇宙科学研究所広報委員、国際科学映像祭実行委員など。幼児から児童生徒、年配者までを対象に幅広いプラネタリウム運営を企画実施したほか、天文分野の普及活動、図録などの執筆を行う(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Gamemaker_K
8
科学的な記述はよく分からないところも多かったけど、木星にしても土星にしても非常にフォトジェニックな星なので図版や写真を追いかけているだけでも楽しかった。…昔、天文台の望遠鏡で土星を初めて見た時の衝撃はまだ身体に色濃く残っている。感動と、得体の知れぬ漠然としたぞわぞわ感とが猛烈な勢いでかき回されたような。2020/04/19
芙蓉葵
1
木星と土星という太陽系ガス惑星について鑑賞のコツや探査の歴史などを写真も多く分かりやすくまとめられた図書。学校の地学の時間に扱ったガリレオ四大衛星やタイタンなど、より詳細に知ることができる。特に面白いと感じたのは5章と6章で、5章は観測機の歴史、6章は惑星形成のメカニズムについて書かれている。各観測機は名前は知っていても目的やどのような調査が行われたのかは知らなかったので、科学の進歩を感じることができた。惑星形成はグランドタックモデルという惑星の移動という途方もない仮説を知ることができ心が躍った。2024/10/08
竜王五代の人
1
観測の見どころから、衛星も含めた科学的特徴、それぞれに送り込まれた観測機まで、図解多めで(内部構造の図解が多いところはよい)分かりやすくまとめた良本。土星の衛星で公転と自転が同期して、同じ面を土星に向けたままのものが多いことは不思議ではないが、つまりは公転軌道の前面・後面といったものまで固定されていることには今まで思い至らなかった。それによって特徴があるということは、やっぱり前面は汚れやすいとかあるのだろうか? 衛星から横から見たら輪は見どころないというのも確かにそう。2022/01/25