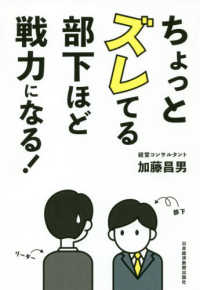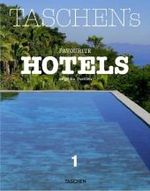内容説明
邦人のタテとなりソ連機甲部隊の侵攻を阻止したわずか一個旅団の戦争。敗戦を迎えてなお、ソ連・外蒙軍から同胞を守るために軍・官・民一体となって力を合わせた人々の真摯なる戦いを描く感動作。
目次
第1章 蒙古桜の花ひらくとき
第2章 銃剣の平和が崩れた日
第3章 迫るソ蒙軍阻む軍旗なき兵団
第4章 日本人引揚げを守った肉弾の壁
第5章 夜霧にまぎれ敵前撤退
第6章 奇跡の引揚げを支えたもの
第7章 残された人々の苦難
著者等紹介
稲垣武[イナガキタケシ]
昭和9年、埼玉県に生まれる。東京大学文学部西洋史学科(技術思想史専攻)卒業。朝日新聞入社、「週刊朝日」副編集長を経て平成元年退社、フリージャーナリストとなる。「悪魔祓いの戦後史」で第3回山本七平賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
yoshida
123
これは後世に伝えられるべき記録である。昭和20年8月20日の内蒙古。約4万人の邦人を引き揚げさせる為に、約5千人の日本軍「響兵団」はソ連軍と戦う。既に日本軍は敗戦により武装解除の命令が下っているなか、例え逆賊と呼ばれても、邦人保護の為にソ連軍と戦うと宣言し実行した軍司令官の根本中将以下響兵団と官吏の自己犠牲は素晴らしい。満州での関東軍との何たる違いであろうか。既に戦争が終わっても、邦人脱出の為にソ連軍と戦い散華された方々は永く顕彰されるべきである。敗戦という混乱の中でも冷静に行動した人々の姿に胸打たれた。2018/07/29
ヘタ
12
先日読んだ『四万人の邦人を救った将軍―軍司令官根本博の深謀』が根本中将個人に焦点を絞っているのに対して、本書は各隊リーダーシップ層の個々人、兵の方々、それぞれの在留邦人視点での作戦・引揚げについての話。やっぱ、兵隊の方々の心の揺れ動きが印象に残る本でした。軍という感情のない一枚岩の物体などではなく、手足の生えた人様が戦っているのだという当たり前のことを強く感じました。2020/04/23
スー
12
四万人の一般人を逃がす為に五千人の兵団がソ連軍を防ぐ為に踏みとどまり、圧倒的な火力を相手に苦戦する。民間人を素早く逃がす為に一時避難だから荷物は最小限と嘘をつく。しかし後に軍は民間人を見棄てて逃げたうえに嘘をついたと恨まれる事に。昭和55年にこの兵団の奮戦が報じられ当時の避難民から沢山の感謝の手紙が届く。終戦を知り帰国を夢見ながら戦地に倒れた兵士達も喜んだだろう。それにしても日本軍は陣地に籠り守備に徹していると強いな。2017/05/26
もちもち
6
自衛隊は日本人を守るためにあるというのは知っていたが、旧日本軍も日本人を守るために存在していたと確信。 日本の主流メディアじゃあ軍人は一番に逃げたと言われがちだけど…2021/11/08
H
4
終戦後内モンゴルの日本人をソ連軍から守るために戦った部隊がいた。こういう歴史は決して忘れてはいけない。悲惨を極めた満州との違いは凄まじい。2023/05/06