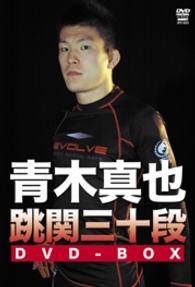内容説明
太平洋戦争末期に登場し、その驚異的な性能と優れたパイロットの技量によって本土上空の戦いにその名をとどろかせた日本海軍最後の主力戦闘機「紫電改」―わずか四百機余の生産数と半年足らずの活躍期間にもかかわらず、日本戦闘機の終焉を飾った名機にたずさわった人々の熱き情熱を綴る感動のノンフィクション。
目次
プロローグ―初陣の日
第1章 大いなる助走
第2章 難問への挑戦
第3章 俊翼飛ぶ
第4章 戦火の中で
第5章 終焉のとき
エピローグ―名機は死なず
著者等紹介
碇義朗[イカリヨシロウ]
1925年、鹿児島生まれ、東京都立航空工業学校卒。陸軍航空技術研究所をへて、戦後、横浜工業専門学校(現横浜国立大学)卒。航空、自動車、鉄道などメカニズムと人間のかかわり合いをテーマにドキュメントを発表。航空ジャーナリスト協会会員。横浜ペンクラブ会員。自動車技術会会員。カナダ・カーマン名誉市民(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
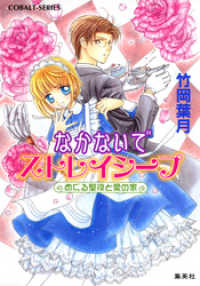
- 電子書籍
- なかないでストレイシープ めぐる聖夜と…
-

- DVD
- 失われた週末