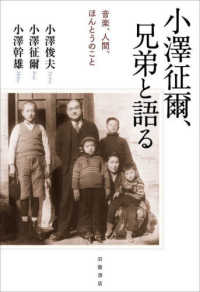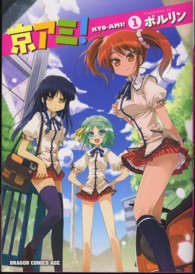内容説明
輸入戦車で編成された機甲部隊誕生から本土決戦に配備された車種と数量まで、機械化の苦手な日本陸軍のなかにあって特異な進化をとげた戦車の破竹の歩みをイラストとともに描く話題作。国産戦車第一号のエピソード、機動運用の訓練、そしてM4戦車との戦闘法など、歴戦の機甲将校が人車一体のノウハウを綴る。
目次
歌で綴る戦車史
戦車の草分けは?
国産戦車の誕生
ディーゼルエンジンの採用
国産戦車の初陣
戦車部隊の増設
昭和の軍神・西住戦車長
異彩を放った戦車将校
戦車士官候補生、見参
若獅子、少年戦車兵〔ほか〕
著者等紹介
寺本弘[テラモトヒロシ]
大正10年、奈良市に生まれる。陸軍士官学校卒業(54期)。陸軍では、機甲(戦車)将校として、戦車第1連隊(久留米)の小・中隊長、戦車第1師団の参謀部幕僚を歴任。この間、マレー、シンガポール、ビルマの進攻作戦に参加する。終戦直前に本土防衛のため満州から移動し、栃木で終戦をむかえる。戦後は自営の後、陸上自衛隊に勤務。退職後はNKK直系のNKH(株)、日動火災海上保険(株)などの顧問をつとめる。平成13年1月歿
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
好古
2
陸軍、海軍よもやま話のような、戦車兵のこぼれ話を期待したが的外れだった。ない事はないがほとんどは淡々と主にマレー戦線でのエピソードが語られる。これと言って特に特筆すべきと感じた小話も無かった。しかしノモンハンの教訓を取り入れずそのまま対米英戦に突入した結果、M3軽戦車にすら複数の97式で側面に榴弾砲を叩き込んでやっと五分という始末。M4に至っては33tなのだから手に負えない。(M3は12t)そして戦車の肉薄攻撃という愚行が行われた。戦争は窮すればする程、狂気の許容の閾値が拡大していくのだなと思った。2024/12/05
産廃屋
2
司馬遼太郎の功績か、日本軍愚行の象徴的存在ともみなされている戦車とその乗員についての一編。戦車兵の心理、戦闘の実態は意外にわかりにくく、そもそもチハあたりにどうやって乗員が乗っていたのかすらよくわからなかったのだが、豊富なイラストつきの本書を一読し、多少は見通しがよくなった。2010/06/13
江川翔太郎
1
日本の戦車の歴史と実戦での様子がイラストと共に書いてあり、読みやすかったです。 実戦編はマレー作戦とビルマ作戦での体験が書いてあり、勝利を収めた初期の作戦でも思いの外撃破されそうになる場面が多く、戦争の厳しさを学びました。 ビルマ作戦時に行われたm3に対する射撃試験では砲弾が砕け散ったと書いてあり、この時点でチハ車の火力が不足していた事に驚きました。 軍刀と拳銃についても記述があり、拳銃は射撃によって恐怖を和らげ、軍刀は精神面の支えになっていてどちらも実用性よりも精神面での効果が大きいことが分かりました。2019/08/19
-

- 電子書籍
- ユリ熊嵐 (下) 【小説版】