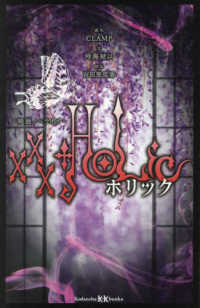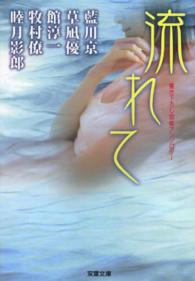内容説明
大戦末期の日本潜水艦の非情なる戦い。伊五十六潜に赴任した若き軍医中尉が、比島東方沖の深度百メートルで体験した五十時間におよんだ米駆逐艦との想像を絶する死闘―最高室温五十度に達する閉ざされた地獄の艦内で、搭乗員たちは黙々と耐え、真摯にその職責を全うする。汗と涙の滴りを見つめる感動の海戦記。
目次
前編(伊号第五十六潜水艦;艦内生活第一日;襲撃訓練;軍港の表情;出撃に備えて ほか)
後編(表彰状;渠底;人間魚雷;猜疑;決意 ほか)
著者等紹介
齋藤寛[サイトウカン]
大正5年10月、東京小石川に生まれる。九段中学卒。昭和18年、慶応大学医学部卒。23年、厚生技官。33年、医療法人財団海上ビル診療所所長に就任。42年(財)労働医学研究会、八重洲口診療所所長、ついで理事となる。富士銀行嘱託、丸山製作所、池袋病院、前沢化成工業、日鉄商事の各顧問ほかを務める。昭和59年4月歿(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。