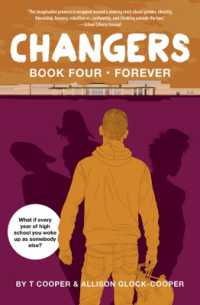内容説明
戦場における強力な“制圧兵器”として重要な地位を確立させた大砲―榴弾砲、加農砲、迫撃砲や戦争末期に開発された噴進砲など、幕末期の輸入砲に始まり、昭和の新型砲まで写真・図面四百五十余点を駆使して網羅した日本の陸戦兵器の決定版―諸外国の影響をうけつつ独自の発達をとげた日本陸軍火砲を徹底研究する話題の入門シリーズ。
目次
第1章 火砲の誕生(欧州における火砲の発達;日本への火砲の伝来と発達)
第2章 近代火砲の発達(四斤野山砲の採用;普仏戦争を制したクルップの火砲 ほか)
第3章 火砲と弾薬の技術(発射速度の変化;射程、射界の増大 ほか)
第4章 日本の代表的火砲(九〇式野砲;九四式山砲 ほか)
著者等紹介
佐山二郎[サヤマジロウ]
昭和22年、岡山市に生まれる。拓殖大学商学部卒業。会社勤務のかたわら、火砲を中心とした軍事技術史の研究に勤しむ(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
しいかあ
0
野砲や山砲、榴弾砲に加農砲、臼砲迫撃砲高射砲……etcetc、最低限これらの火砲の種類について知っていないとそもそも話が始まらないような「入門書」とはいったい…(うごごご!)。というか、これ大砲入門じゃなくて「日本陸軍火砲史概説」じゃねーかコノヤロー。amazonで見てみたら、全くの初心者が大砲についての基礎的な知識を得るには、同じ著者の「高射砲」の前半部分のほうが適しているらしい。そっち読むか……。2016/03/29
subuta
0
図表と写真が非常に多く、ページ数の割りに読み終わるまで時間がかからなかった。砲の部品や海外の地名など、日常的に使わない漢字にフリガナを振ってくれたら、より「入門」らしくなったのではと思う。2016/01/30
shimada1986
0
日本の火砲の発展について知ることができる。図版や資料も豊富。ただ、旧軍の火砲に記述範囲は限られており、自衛隊の火砲に触れられていないのは残念。自衛隊のものは機密上詳しく記述できないのだろうが。2011/06/19
へべれけ軍曹
0
「入門」と言うタイトルなんだから最低でも歴史、仕組み、用語の説明くらい必要だと思うが。専門用語の説明もなく、日本陸軍の大砲のカタログスペックと開発経緯の羅列。大砲の側面図見せられても。2021/10/01
tkm66
0
義祖父との話で必要あって購入、との覚えが。2004/08/23
-

- 和書
- 錬金術 文庫クセジュ