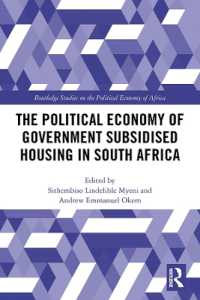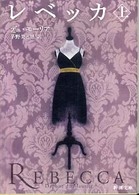内容説明
「日本最高の傑作戦闘機」と米軍に語らしめた日本陸軍の二千馬力戦闘機・疾風―日米開戦とともに設計に着手され、苛烈さを増す最前線の期待を担って登場した高性能機。その誕生までの設計陣の足跡、奇蹟のエンジンと呼ばれた“誉”発動機の開発秘話、比島・沖縄戦での疾風の奮戦を描く感動のノンフィクション。
目次
第1章 大戦前夜の迷い
第2章 軽戦から重戦へ
第3章 二千馬力戦闘機計画
第4章 奇蹟のエンジン「誉」
第5章 期待を担う大東亜決戦機
第6章 出陣の秋
第7章 全戦闘機、特攻出撃せよ
第8章 悲しきフィナーレ
著者等紹介
碇義朗[イカリヨシロウ]
1925年、鹿児島生まれ、東京都立航空工業学校卒。陸軍航空技術研究所をへて、戦後、横浜工業専門学校(現横浜国立大学)卒。航空、自動車、鉄道などメカニズムと人間のかかわり合いをテーマにドキュメントを発表。航空ジャーナリスト協会会員。横浜ペンクラブ会員。自動車技術会会員。カナダ・カーマン名誉市民(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
イプシロン
48
戦中派の著書を読むと、当時が濃厚に匂いたち、うち顫える。ことの善し悪しはまず擱いて、当時の人びとに思いを馳せ、その上に現在のわれわれがあると強く思うからだろう。今日わが国の工業技術力を知る身からすると、おおよそ想像出来ない労苦を強いられた時代があった。しかし足りないからこそ魂を燃やし、知恵を絞って必死になることができた。一部には、あろうがながろうが精神論を振りかざす傲慢さがあったのは残念だが。過剰と不足は複雑微妙な感覚を呼び起こすものだと感じた。老子曰く「知足者富/強行者志有/不失其所者久/死而不亡者寿」2020/01/30
Miyoshi Hirotaka
30
イノベーションという表現がビジネスで多用され、安売り感が否めない。本物のイノベーションは命を削った先にある。目的のために組織を最適化し、メンバーは最大能力を短期間に爆発的に発揮する。技術の限界を超えるイノベーションは顧客の声を聴くことではなく顧客の創造。国産ロケットのパイオニア糸川英夫、自動車エンジン開発の中川良一など、戦後も別分野でイノベーションを起こし続けた偉大な技術者が実名で登場。対戦した米軍から日本最優秀戦闘機と評価をうけた技術開発には将来も参考となる事例が満載。これが歴史を直視するということ。2015/12/05
スー
17
日本最高性能の戦闘機疾風、軽戦に取り付かれた陸軍を説得して重戦の開発を納得させるか、疾風を高性能機にするエンジン誉の開発、エンジンの性能を引き出すプロペラ選定に寝る間も惜しみ研究した技術者達の苦労と疾風の稼働率をあげる為に働いた整備士達の努力がよく分かりました。この高性能機が登場したのは開発者の努力は勿論ですが、日本の資源が乏しい苦しい状態を知恵を絞り出し結果産み出した物でしたが、産まれた機体は乏しい資源の為に実力を出しきれない皮肉。当時の日本の技術と資源の無さが切なかった。2018/05/05
zunbe
4
疾風の開発の基盤となった、九七戦、隼、鍾馗の開発の話から始まり(なぜか飛燕は、スルーされているが…)、誉エンジンの開発や、他の書籍ではあまり触れられないプロペラなどにも触れ、更には、いかにして陸軍は軽戦一辺倒から重戦重視に移っていったかなどの流れも書かれていて、興味深く読ませて頂いた。巻末になるにつれ、技術的な話から外れ、連合軍の大軍勢との絶望的な戦い、特攻隊、空襲などの話が多くなり、重い内容になってしまうが、様々な苦難を跳ね返して最高の戦闘機を開発した技術者の苦心がよくわかる書籍だった。2015/04/08
Machida Hiroshi
3
本書は、日本陸軍の数少ない二千馬力級戦闘機・疾風の設計から始まり、奇跡のエンジンと呼ばれた「誉」の開発や、最終的に最高傑作機と呼ばれた疾風の戦いの様子までを描いたノンフィクション戦記です。もっとも誉エンジンが、その能力を発揮したのは、オクタン価の高い良質のガソリンを使い、良質のオイルを使った場合だったようですが、それでも、戦時中の粗悪ガソリン、粗悪オイルでもなんとか故障少なく、飛び続け、成果を挙げたのは、隼、零戦、疾風に使われた中島飛行機の空冷エンジンだったようです。僕は平和な時代の技術者で幸せだったな。2017/04/27
-
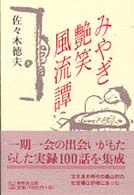
- 和書
- みやぎ艶笑風流譚