出版社内容情報
現在の栃木県さくら市喜連川に
陣屋を置いた名門足利一族の藩
大名とは徳川家の直接の家臣で一万石以上の武士のこと。しかし、その定義に当てはまらない武士がいた。それが喜連川氏である。喜連川氏は、室町幕府を開いた足利尊氏を祖とし、江戸幕府を開いた徳川氏とは比べ物にならないほどの歴史と由緒を誇る。名門一族を大切にする江戸幕府によって、喜連川氏はわずか5000 石ながら大名の地位についた。しかも、大名に義務付けられている参勤交代や、妻子を江戸に住まわせることも免除されていた。異例づくしの喜連川藩が、江戸時代、激動の幕末をどう生き抜いたかを紹介する。
【目次】
内容説明
喜連川家は「国勝手」。日光社参役などの諸役も免除、参勤交代の義務もなく、「公方様」「御所様」と呼ばれていた喜連川公。さくら市の今も、荒川の鮎、お丸山の桜に暴れ神輿、温泉でゆったり栄える町。
目次
第一章 喜連川藩の誕生 源義家から、源頼朝、足利尊氏を経て喜連川藩の誕生までを辿る。
第二章 喜連川藩の格式 喜連川藩は幕府から様々な特権が与えられ、世間からは特別視された。
第三章 名君揃いの喜連川藩主 四代から十代までの歴代当主の事蹟を追う。
第四章 喜連川藩の財政と喜連川宿のにぎわい 貧乏な藩ゆえ苦労も多かったが、奥州道中の宿としてにぎわった。
第五章 喜連川家の学問と医学、諸芸 藩校翰林館が設置されて学問が盛んになり、文化が栄えた。
第六章 幕末の喜連川藩 養子縁組が続き、藩政の混乱も起きたが、それを乗り越え維新を迎えた。
著者等紹介
岡一雄[オカカズオ]
昭和33年(1958)、栃木県さくら市生まれ。獨協医科大学卒。岡医院院長。塩谷医療史研究会代表
小竹弘則[コタケヒロノリ]
昭和40年(1965)、栃木県さくら市生まれ。現さくら市ミュージアム―荒井寛方記念館―館長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
-
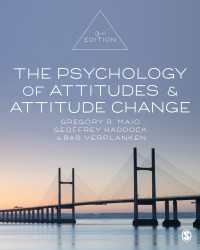
- 洋書電子書籍
- The Psychology of A…
-
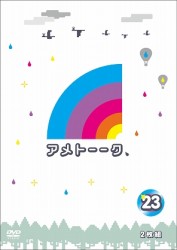
- DVD
- アメトーーク!DVD23







