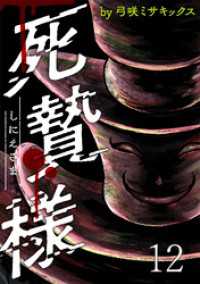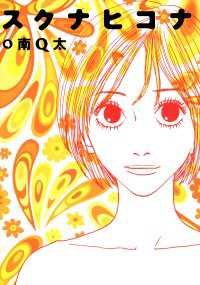出版社内容情報
駿河国の東部、地上・海上ともに交通要衝の地・沼津。城下町と宿場町、武士と町民の文化が混在し栄えた沼津。その歴史と文化を活写。
樋口雄彦[ヒグチタケヒコ]
1961年、静岡県熱海市生まれ。国立歴史民俗博物館・総合研究大学院大学教授。博士(文学、大阪大学)。著書に『旧幕臣の明治維新 沼津兵学校とその群像』、『沼津兵学校の研究』、『静岡学問所』、『第十六代徳川家達ーその後の徳川家と近代日本』、『敗者の日本史17 箱館戦争と榎本武揚』、『人をあるく 勝海舟と江戸東京』、『幕臣たちは明治維新をどう生きたのか』など。
内容説明
近世初期は大久保家、中絶後、後期は水野家が治めた。東海道の宿場とともに発展した五万石の城下町。
目次
第1章 前史‐江戸時代前半までの沼津―沼津に築かれた三枚橋城には、江戸初期に大久保氏が二万石で入る。(戦国時代の三枚橋城;江戸初期―大久保忠佐の沼津藩;藩がない時代)
第2章 沼津藩の成立―江戸後期、水野氏を藩主とし沼津藩が成立、沼津は再び城下町となった。(水野忠友による立藩;老中水野忠成による幕政;領地と領民)
第3章 沼津藩の展開―主君への奉仕と藩の経営にあたった藩士たち。彼らはまた文化の担い手でもあった。(藩士の身分と生活;藩士が担った文化)
第4章 海防と幕末の動乱―対外危機の中、伊豆での海防に奔走。戊辰の戦乱では早々に新政府に恭順する。(海防・砲術・安政大地震;戊辰戦争と藩政改革)
第5章 明治維新のあと―明治初年の菊間転封、そして廃藩後も旧藩主・藩士らの交流は続いた。(維新後の転封―菊間藩;分家・旗本水野春四郎;明治を生きた旧主と旧臣)
著者等紹介
樋口雄彦[ヒグチタケヒコ]
1961年、静岡県熱海市生まれ。国立歴史民俗博物館・総合研究大学院大学教授。博士(文学、大阪大学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。