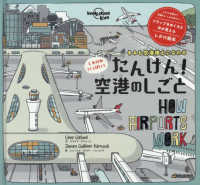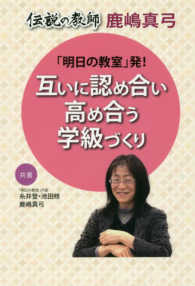内容説明
いまも生きているサンカたち。彼らの綿密な聞き取りから、サンカへの幻影が解き放される。
目次
第1章 ある家族の風景
第2章 武蔵サンカの生態と民俗
第3章 箕と箕作りの村、箕作りの民
第4章 移動箕作りたちのたそがれ
第5章 ウメアイ考
第6章 三角寛『サンカ社会の研究』の虚と実
第7章 サンカの名義と系譜について
著者等紹介
筒井功[ツツイイサオ]
昭和19年、高知市に生まれる。もと共同通信社記者。現在は「日本竹細工研究所」を主宰し、主に非定住民の生態・民俗や、白山信仰の伝播過程の取材をつづけている
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
岩間 宗達
4
読了。米原万里さんの「打ちのめされるようなすごい本」より。「サンカ」という言葉を知ったのも初めてであった。著者が巻末で書いている通り、この著作ができた時くらいが実際にサンカの姿を記憶している人間と接触するラストチャンスだったのでは無いだろうか。令和の今に同様の研究を試みても2次資料に当たるのが関の山かと。三角寛批判は多いが、サンカを知るには貴重な資料であることは間違い無いと思う。2023/01/31
in medio tutissimus ibis.
3
所謂研究上のサンカは箕作、竹細工、川魚漁などに従事し、閑期には神事芸能活じき日雇いなどに従事する、定住あるいは漂泊の民である。箕は竹、あるいは藤などの材料からなる脱穀後の分別に用いる農具であり、一般に高価かつ修繕によりかなり長持ちする。箕には概ね竹が使われるが、藤等の系統では全工程が小刀一本で可能となる。云々。ウメアイと称される象徴的なこの道具が両刃とされるのは、一本で酷使する上でスペアがあった方が便利だからではないか。また箕の需要の不安定さが、箕作をして広域を漂白する生活に向かわせたのかもしれない。2019/01/25
りんか
2
中世流浪民や木地師などに興味があるのでその流れで手にした一冊。三角の研究資料の書き方には引っかかるものを感じていたので本書でやはりそうだよなぁと腑に落ちる部分があった。証言者は年々減って行き、全体が解明されないままに消えていくのもまた定住しない民らしい。こうして歴史にも記録にもほとんど痕跡を残さず消えて行った文化風俗はきっとサンカ以外にもあったのだろう。2014/12/15
莉野
0
箕作りが用いる両刃の小型『ウメアイ』にはどんな背景が、禁忌があるのだろうか、東北北部と埼玉の箕作り家男女を結びつけた糸はどこにあるのか、今もひっそりと社会の路上で張られているのか…荻原規子さんの『RDG』に出てくる山伏や、恩田陸さんの『常野物語』の一族がふっと浮かんで来た。上の2冊は小説だが、類似点があり、連想すると止まらない。 サンカ、という言葉は柴田よしきさんの小説で知ったことで、なんとなく昭和初期まで存在した流浪の民だと思っていたが、本書で少しはどんなにものかわかってきた。(続く)2010/07/12
-
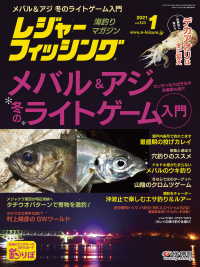
- 電子書籍
- レジャーフィッシング 2021年 1月号