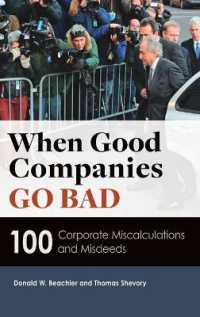内容説明
水彩画のような翅、珍奇な角―。ビワハゴロモの知られざる美と造形に迫る、世界初の図鑑。
目次
中南米のビワハゴロモ(世界に冠たる奇虫群―ユカタンビワハゴロモ属;奇と美を兼ね備える―リュウノカオビワハゴロモ属;そのまま服にしたくなる意匠―ミズタマビワハゴロモ属;王様の椅子を頭にのせて―ノコギリビワハゴロモ属;小さいが独特―その他の中南米のビワハゴロモ亜科 ほか)
アジアのビワハゴロモ(鼻高々な個性派ぞろい―インド~インドシナ半島のテングビワハゴロモ属;島々の文様―フィリピンのテングビワハゴロモ属;まさに多様性の坩堝―マレー半島・大スンダ列島のテングビワハゴロモ属;新しい種が続々と―小スンダ列島のテングビワハゴロモ属;小さな天狗―ヒメテングビワハゴロモ属 ほか)
アフリカのビワハゴロモ
著者等紹介
丸山宗利[マルヤマムネトシ]
1974年生まれ。東京出身。九州大学総合研究博物館准教授。北海道大学大学院農学研究科博士課程修了。農学博士。専門はアリやシロアリと共生する昆虫の分類学や系統学で、アジアでは第一人者。研究や学生の指導に加え、昆虫の面白さや美しさを多くの人に伝えることをモットーとし、幅広いメディアやSNSで情報発信している(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
すぱちゃん@全てひっくるめて、楽しむものの勝ち
40
ビワハゴロモ。この美しくも妖しい昆虫に初めて出会ったのは、小学校4年生にデパートの催しもの会場で昆虫展を観たときであった。それも奇虫中の奇虫、ユカタンビワハゴロモに、私の目は釘付けになった。中南米に生息し、頭部を横から見るとワニの顔・後翅には大きな目玉模様。ショッキングだったが密かに欲しくなった。販売標本の中に見つけた私だが2万円もする。諦めるしかなかった。大人になって採集に行ったボルネオでは2種のビワハゴロモを採集した。本書で調べてみたところ、ホワイトヘッドテングとスルタンテングだとわかった。すごい⤴️2021/01/08
スリカータ
20
丸山宗利さんの本なので読んでみた。ビワハゴロモ…聞いたことないなぁ?と思ったら、在来種にはいないとのこと。カラフルな紋様の羽を持つが、蛾の仲間ではなくカメムシに近い。カメムシ…で引きそうになるが、世界のカメムシには美しい種が多い。長い鼻?が特徴のものや丸顔がいたり、なんとバラエティ豊かな種類だろう。ビワハゴロモにどっぷりと浸れるマニアック過ぎる図鑑の出版は、元気が出ます。2021/04/13
石油監査人
15
ビワハゴロモとは、蝶のような美しい翅とセミのような太い胴体を持ち、さらに、多くの種類の頭部には天狗の鼻ような長い角があるという、変わった形態の昆虫で、主に熱帯地域に生息しています。この本では、世界各地から珍しいビワハゴロモを美しい写真とともに紹介していて、特に、これまで見たことのない形態のビワハゴロモの写真は、進化の面白さを感じさせてくれます。例えば、ワニのような頭部を持つものや、タツノオトシゴのような顔を持つもの、さらには、白い蝋状物質を胴体からぶら下げているものなどは、何度見ても不思議に感じます。2022/04/10
わらわら
11
「ビワハゴロモ」名前も神秘な昆虫を想像する。誰がデザインするのか、不思議な形、色合い、模様。あってみたいが日本にはいないらしい。いやいや海外でも合うことができるのは稀な事らしい。丸山宗利氏が図鑑にしたことで「ヒトハゴロモ」を知ることができた。絵を描く孫に送ろうか…手元に置いて部屋に飾ろうか悩む。この美しい色は孫にも教えたい。2021/04/19
テイネハイランド
7
「ツノゼミ ありえない虫」「きらめく甲虫」「驚異の標本箱 -昆虫」に続く丸山さんの昆虫写真本ということで図書館から借りてきました。しかし「ツノゼミ」や「カブトムシ」と違って今回の「ビワハゴロモ」は生理的に嫌悪感が先立って(ワックスのような物質をその体から分泌するそうです)、そのカラフルな模様もあまり美しいとは思えず本書を過去の昆虫写真本に比べると楽しめませんでした。日本では見ることのできない種族が網羅されていますので労作だとは思いますが、私には合わなかったみたいです。2023/03/24