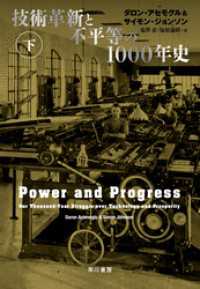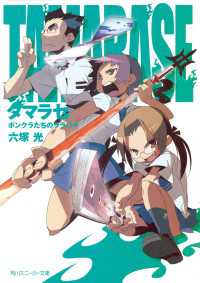内容説明
我々の社会が直面している「現実」を直視しないことには始まらない。現実を直視せず、精神力でなんとかするという態度こそ、この社会で幾度も繰り返されてきた悲劇ではなかったか。誰も語らなかった難問を注目の若手社会学者が解く!
目次
第1章 不寛容の本質に迫る
第2章 我々は「豊か」になったのか、「貧しく」なったのか
第3章 なぜ若者は「反自民、反安倍」ではないのか
第4章 「イノベーター」と「生活者」の共存は可能か
第5章 少年犯罪と隠れた格差
第6章 研究環境と高等教育の変容がもたらした違和感
著者等紹介
西田亮介[ニシダリョウスケ]
社会学者。東京工業大学リベラルアーツ研究教育院准教授。博士(政策・メディア)。専門は公共政策の社会学。情報と政治、情報化社会のジャーナリズム、無業社会等を研究。1983年京都生まれ。慶應義塾大学総合政策学部卒業。同大学院政策・メディア研究科修士課程修了。同後期博士課程単位取得退学。同助教(有期・研究奨励2)、(独)中小機構経営支援情報センターリサーチャー、立命館大大学院特別招聘准教授などを経て、現職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
おさむ
41
鋭い論考で知られる若手社会学者の西田氏の新刊。「昭和の面影」に幻想を抱き、マインドチェンジができないことが、様々な場面で実態と認識のギャップを生んでいるとの指摘はうなずける。また、かつての知識人に変わって平成日本ではイノベーターが重宝されているが、彼らと生活者の利益は相反するとの主張もひざを打った。同じ社会学者の古市氏にも感じたが、最近の若手学者はどこかに世代間格差へのルサンチマンのようなものを感じる。これが右肩下がりの世代の特徴なんだろうか?2017/02/22
こも 旧柏バカ一代
21
昭和の常識が時代の変化に対応出来ない連中が、自身の中にある常識を押し付けて政策を形成する。それによって現実と乖離して行く。それによって余裕を無くしていく人々。産まれてから世の中が変わらないと感知している世代はイノベーションを起こす気を失くす。現在のイノベーター達は、、時代の変化に対応出来ない連中が押さえつけて、現在は海外に行ったり、靴を舐めて利権側に行く。少年院の子供達も家庭によっては全く教育を受けておらず、より深刻になっていく。最後の章では大学の予算について、文科省って本当に碌な事しないよな、、民間もか2023/07/19
tolucky1962
10
若手社会学者が頑張ってデータを集めて論を進めようとしている。昭和の良き日々で測ろうとする年配と、もうあのころには戻れないと悟っている若者の対立と見立てる。そのうえで、若者が苦しまされているのに反安倍にならない不思議、エリートが知識人からイノベータへ移行していること、少年犯罪の問題や、研究環境と高等教育にたいする問題提起など、さまざまな議論をしているが、タイトルの不寛容からは離れている気がする。2017/05/04
hiyu
7
問題の提起に関して異論はない。中には頷けるものもある。しかし、著者には非常に申し訳ないのだが、P27のシェーマはピンとこなかった。不寛容の定義というか、概念も漠然として印象であった。自分の理解の問題だろうか。また、若者の見方としては著者の指摘の通りで良いのか、それも悩む。2017/04/08
失速男
6
現代の不寛容とその構造を論じる本なのだが、著者の不寛容な社会と私の思う不寛容な社会が違うのか、スッキリしなかった。2~6章は果たして不寛容の本質を追究した文なのか、バカな私には分からなかった。 昭和の時代はゴミは捨て放題、タバコは何処でも吸い放題、ヤクザに頼ってもよかったし、ネットに書き込む代わりにぶん殴ってたし、盗んだバイクで走り出してもよかった。今はそういうの許さない、がエスカレートし、些細な事に”個人的な正論”を言う環境が充実しているだけのような気がするが、誰かバカでも分かるように解説して欲しい。2017/03/08