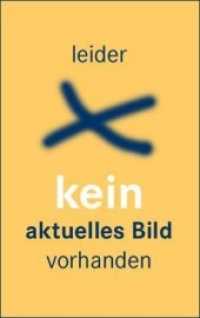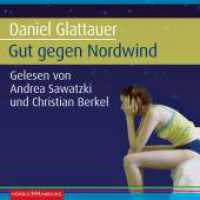出版社内容情報
「犬が独りでお伊勢参りに行ったって? そりや愉快、べらぼうだい!」
江戸時代、人と動物たちはどのような関係であったのか?
西洋文化が流入する以前の日本人と動物たちとのかかわりを、古文書読みに長けた動物好きの専門家たちが描く。
犬、牛、馬、鹿、猪、鷹、鶴、猫、鳥、獺、熊、鯨……。江戸時代の動物たちが勢揃い! 狩る、食べる、愛でる、働いてもらう、薬にする、旅に行かせる……など、実に様々な人と動物たちの関係を古文書や浮世絵などから読み解き、動物とともにある日本人の姿が浮き彫りに。
動物愛護やアニマルウェルフェアを考える上でのヒントも満載!
有名な「生類憐みの令」は江戸時代の人々をどう変えた? 現代と同じようなペットブームがあったって本当? など 知っているようで知らない意外な話も続々。多彩な文化が花開いた江戸時代は、動物たちを通して見ても、とっても面白い!
内容説明
江戸時代、人と動物たちはどのような関係であったのか?西洋文化が流入する以前の日本人と動物たちとのかかわりを、古文書読みに長けた動物好きの専門家たちが描く。
目次
第一章 犬の江戸時代
第二章 牛と馬が支える江戸時代の暮らし
第三章 狩られる鹿・猪たち―徳川将軍の「鹿・猪」狩り
第四章 鶴と鷹の江戸時代―徳川将軍と「御鷹之鶴」
第五章 江戸のペットビジネス
第六章 薬となった動物たち
第七章 鯨と江戸時代人
著者等紹介
井奥成彦[イオクシゲヒコ]
慶應義塾大学名誉教授。1980年慶應義塾大学文学部卒業、1986年明治大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得退学、博士(史学)。九州大学石炭研究資料センター助手などを経て2006年より慶應義塾大学文学部教授、2023年より同名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
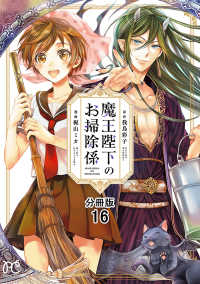
- 電子書籍
- 魔王陛下のお掃除係【分冊版】 16 プ…